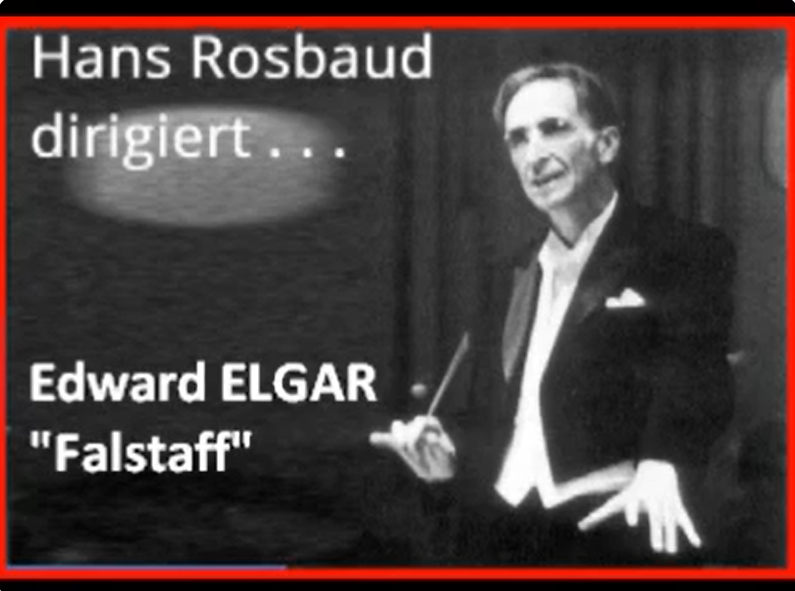エルガー暗黒期に灯された知性の炎 ― ハンス・ロスバウトとSWR交響楽団による《ファルスタッフ》
こんな録音があったとは!
1956年に収録されたハンス・ロスバウト指揮、南西ドイツ放送交響楽団(現SWR交響楽団)によるエルガー《ファルスタッフ》は、エルガー演奏史の文脈において極めて貴重な録音である。1950年代はエルガー作品の受難期であり、母国イギリスでさえエルガー作品はほとんど顧みられていなかった時代である。その中で、ドイツ圏の指揮者がこの作品を演奏していたという事実自体、異例中の異例である。ロスバウトの知的好奇心と音楽的誠実さがいかに広い射程を持っていたかを示す証左である。
ロスバウトの《ファルスタッフ》は、エルガー特有の英国的感傷をほぼ排除し、構築的・分析的に音楽を解体し再構築するという、実に“ドイツ的”なアプローチをとっている。冒頭「ファルスタッフとハル王子」ではテンポをやや抑えめに取り、フレーズを明瞭に区切って提示する。ここにはエルガーのロマン主義的表情よりも、シンフォニックな素材展開を明確に見せる意図がある。ロスバウトは感情よりも構造を聴かせる指揮者であり、彼の手にかかるとこの作品はまるでリヒャルト・シュトラウスの交響詩のように、精密な音響建築として姿を現す。実際、この曲はエルガーの作品の中で最もリヒャルト・シュトラウスに接近した作品といわれるだけに、その部分を強調している感じである。
第2部「イーストチープ、宴と眠り」では、彼独自の冷徹なリズム感が際立つ。英国指揮者がしばしば描くユーモアや酔態の温かみはほとんどなく、代わりに奇妙な緊張感が漂う。木管群の妙技は見事であり、線の細い響きながらも、各声部が明快に分離して聴こえる。この抑制された喜劇性こそが、ロスバウトの知的リアリズムの表れである。
「夢想の間奏曲」では、淡い抒情が現れるが、感傷は常に理性の手綱で制御されている。テンポの流れは極めて自然で、細部におけるアゴーギクも控えめ。ここでのファルスタッフ像は“哀れな老騎士”ではなく、“自らの矛盾を冷徹に見つめる人間”として描かれている。ロスバウトの哲学的指向が音に結晶している瞬間である。
後半の「グロスターシャーへの帰還」「新王の登場」では、ロスバウト特有の鋭い対位法的処理が光る。対旋律の明確さ、トゥッティにおける声部の整理の見事さは、当時の放送オーケストラの水準をはるかに超えている。終結部「ファルスタッフの死」においても、感情的な高揚を抑え、むしろ静謐な諦念として描く点に、ロスバウトの精神性が如実に現れている。ここには涙よりも、透徹した死の受容がある。
この演奏を現代の耳で聴くと、英国的エルガー像とはまったく異なる、分析的で硬質なファルスタッフ像に驚かされるだろう。だが、そこにはロスバウトならではの「真理を音で掘り下げる」知の姿勢が息づいている。1950年代という、エルガーが世界的に忘れられつつあった時代において、この作品にここまで精緻なアプローチを試みたロスバウトの見識は特筆すべきである。
総じて本演奏は、感情の奔流ではなく、構造の透徹によってエルガーの精神に迫る希有な試みである。エルガーを“英国的情緒の象徴”としてではなく、“ヨーロッパ近代の交響的遺産”として扱った、稀有な記録であり、まさにエルガー暗黒期に灯された知性の炎である。
暗黒期が空けるのは1962年のケン・ラッセルによるBBCドキュメンタリー番組「エルガー」の登場まで待たねばならなかった。