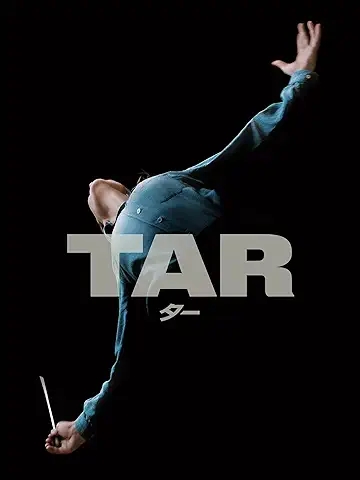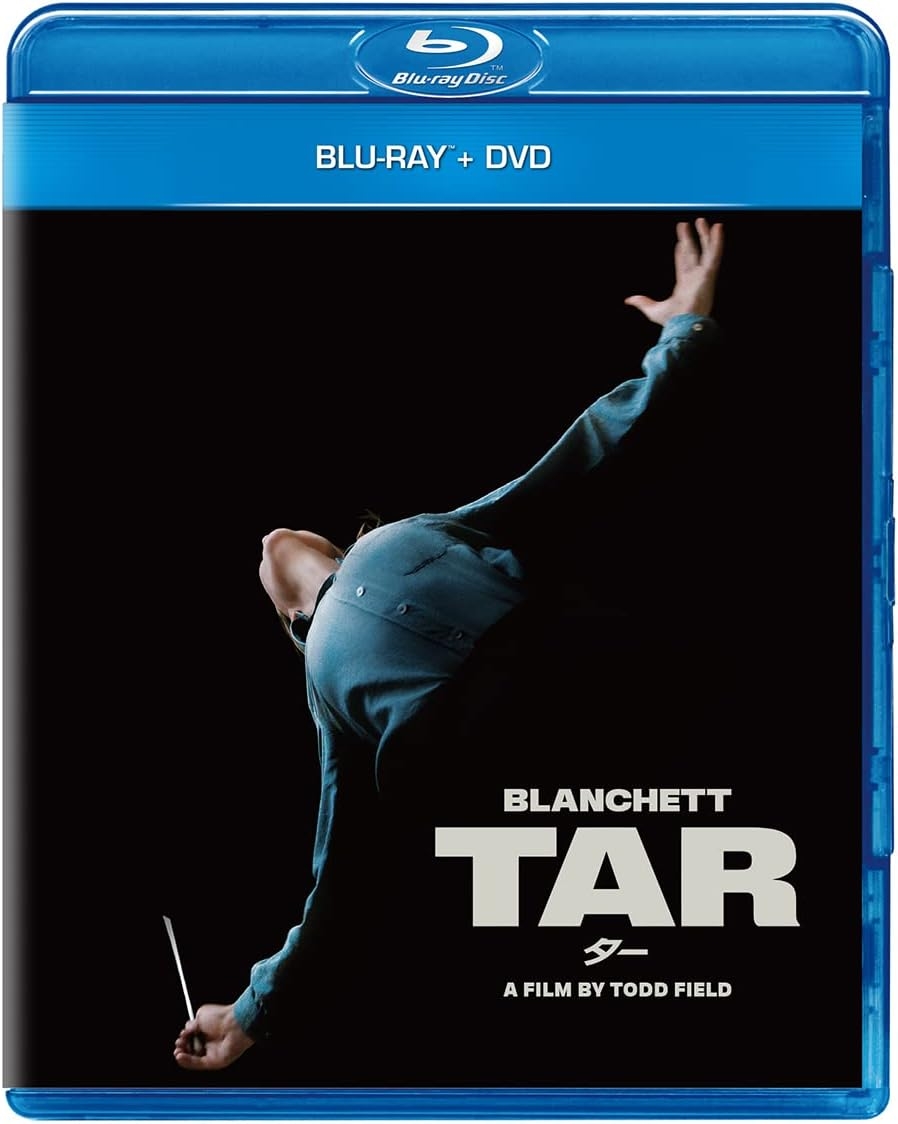映画「ター」について
クラシック愛好家による映画『TÁR』実況付き鑑賞記

クラシック音楽を題材にした映画として注目は集めた「ター」。
一見した感じは、初心者には優しくない映画だなというのが第一印象。
観客ターゲット層は誰なのか?いまいちよくわからない。
ポンポン飛び出すクラシック音楽関連の固有名詞の数々。
そもそもクラシック音楽知らない観客のことを全く想定していない。
レヴァインとデュトワのスキャンダル事件なんかもサラっと出てきたりとか・・・。この事件のことやら、レヴァインとかデュトワを知らないと何のことやらサッパリになるだろう。その事件の説明もされることもない。
まずそこが理解できなければ開始早々に置いてきぼりを食らって2度と戻ってきてはもらえない。
クラシック音楽に興味ない人が観たら、あの業界専門用語オンパレードどこまで理解できるのだろうか?というのがあまりにも多い。
セリフで「DGが」とか、字幕では「グラモフォンが」とか何度もサラっと出てくるが、クラシック音楽ファンならすぐ「ああ、ドイツグラモフォンね」とすぐ理解できるが、一般ピーポーにとってはなんじゃらほい?って感じ。
それを乗り越えたとしても、ストーリーが一筋縄では行かない(ストーリー自体は単純なのだが)。
一度観ただけでは細かい部分の理解が追いつかない。
印象としてはダークなストーリーが淡々と続く。
心理描写や抽象的表現が続き、主人公ターが観ている夢なのか幻覚なのか現実なのかわからなくなる。
今回の主役ターを演じたケイト・ブランシェットが、かつて演じた「エリザベス」もこんな感じだったし、何よりもホアキン・フェニックス主演のDC映画「ジョーカー」のテイストが似ているのだ。
あの「ジョーカー」を楽しめた人は「ター」も面白く観れるかもしれない。
まるでベルリンの街がゴッサムシティに見えてしまったほど。
ジョーカーの闇落ちとターのサクセスストーリーの崩壊の仕方が正にシンクロして見えてしまう(キャンセルカルチャー)。
奇しくも両作品の音楽を担当したのはヒドゥル・グドナドッティルというのも奇遇ではある。とにかくダークで落とし所がよくわからない映画である。
演出の手法がホラー映画っぽいのでホラー苦手な人はやめた方がいいと思う。クローズアップはしていないけど明らかに「幽霊」を登場させている。
それこそ「心霊動画」っぽく。つまり主人公ターは気づいていないだけで彼女の周りで起こる不可解な現象が実は霊障であることを暗に描いているのである。
そのうち出てくるだろうと思わせておいて劇中に起こる不可解な怪現象が誰の仕業なのかが最後まで明かされないまま終わる(ヴィランの存在を匂わせておいて結局その存在が明かされない)。要するにこれ正にターの視点からの描写なので本人が「それ」の存在に気付いていないということになるのだ。
つまり、この狭義の視点からしか見えないイコール現代のSNSを通してしか世界が見えない・・・という現代社会の視点をも表しているといえるのである。
結構深いかもしれないこの映画。
個人的にツボの一つだったのが、ソフィー・カウアー演じるチェリストのオルガ・メトキナがエルガーのチェロ協奏曲をyoutubeでデュプレの演奏に感動したというくだり。
それに対してターが「ああ、バレンボイム指揮の演奏ね」というと「指揮者は誰だが知らない」と答える。バレンボイムなんてどうでもいいと言いたげな演出が憎い。これは笑った笑った。
まとめると・・・・・
1. 観客ターゲット不明問題:
まさしく「クラシック音楽業界の中の人」向けに作られた映画であることは否定できない。固有名詞の連発(レヴァイン、デュトワ、グラモフォン、ジュリアード…)はまさに“内輪ネタ”に近く、門外漢は入り口で振り落とされよう。言い換えれば、本作は**「業界という密室性と崩壊の物語」であると同時に、その密室にアクセスできる者だけが“共犯者”として参加できる劇場型体験**なのである。
「門外漢をあえて振り落とす」ことで、ターの世界そのものを映画形式で体現している。
これは映画的なメタ構造であり、確信犯的に「不親切」な作りにしているのは間違いないだろう。
2. ストーリーのダークさ・視点の限定性:
「夢なのか現実なのか幻覚なのか分からない」
「幽霊」的現象とホラー的演出
「ターの視点からしか描かれない=SNS視点の比喩」
これらはまさに本作最大の特徴である。ターの主観視点に徹底的に縛られていることが、彼女が自分の権力構造や破滅の原因すら“直視できない”という構造的問題をそのまま観客に体感させる仕掛けになっているわけである。つまり、「誰が敵かも分からず、誰に潰されたのかすら分からないまま消えていく」という現代型キャンセルカルチャーの恐怖を映画的に体現している。
それゆえにこの映画は、「ホラー」ではなく「現代社会の寓話」として機能している。
この恐怖は、たとえばハリウッド的正義や明確なカタルシスを持つ“#MeToo映画”とはまったく違う、告発者すら不可視な構造的破滅を描いている点で、じつに現代的である。
3. 「ジョーカー」との類似:
『ジョーカー』が「社会に適応できなかった者の内面崩壊」ならば、『TÁR』は「権力を持った者が適応しすぎた結果、倫理が空洞化していく話」とも言えるかもしれない。どちらも孤独な天才の主観に閉じ込められた地獄絵図であり、ヒドゥル・グドナドッティルの音楽が両者に冷ややかな統一感をもたらしている。
4. オルガのくだりと、ターの「ズレ」:
「バレンボイム?誰それ?」
この場面は、ターという存在がすでに時代の感性とズレていることを示す象徴的な瞬間。彼女の世界観は「巨匠主義」「名盤主義」「指揮者中心主義」に染まっているのに対して、オルガのような若者は、あくまで“感動した演奏”だけに価値を見出している。
ターにとってクラシック音楽は“権力と体系”だが、オルガにとっては“ただのコンテンツ”。
この断絶は、まさに現在のクラシック音楽界が直面している「権威の終焉と感性のフラット化」そのもの。
総評:
『TÁR』は、
クラシック音楽業界の閉鎖性、
ジェンダーと権力の問題、
キャンセルカルチャーの闇、
ポスト権威時代の生きにくさ、
そして人間の崩壊を覗き見るホラー
これらをすべて一つに詰め込んだ、稀有なフィルムでもある。
P.S.
「心霊動画っぽい幽霊表現」――これ、実は本国の批評家でも一部話題になっていた点。たとえば シャワー室に現れる謎の影、ターの部屋に現れる女の影、音のない声のような演出…すべてターの“罪の亡霊”なのだと見る向きもある。彼女が気づいていないからこそ、観客にも見えそうで見えない。それこそ“霊障”という形の象徴。トッド・フィールド監督は、ホラー的演出で心理的罪悪感を映像化したのだと考えられる。
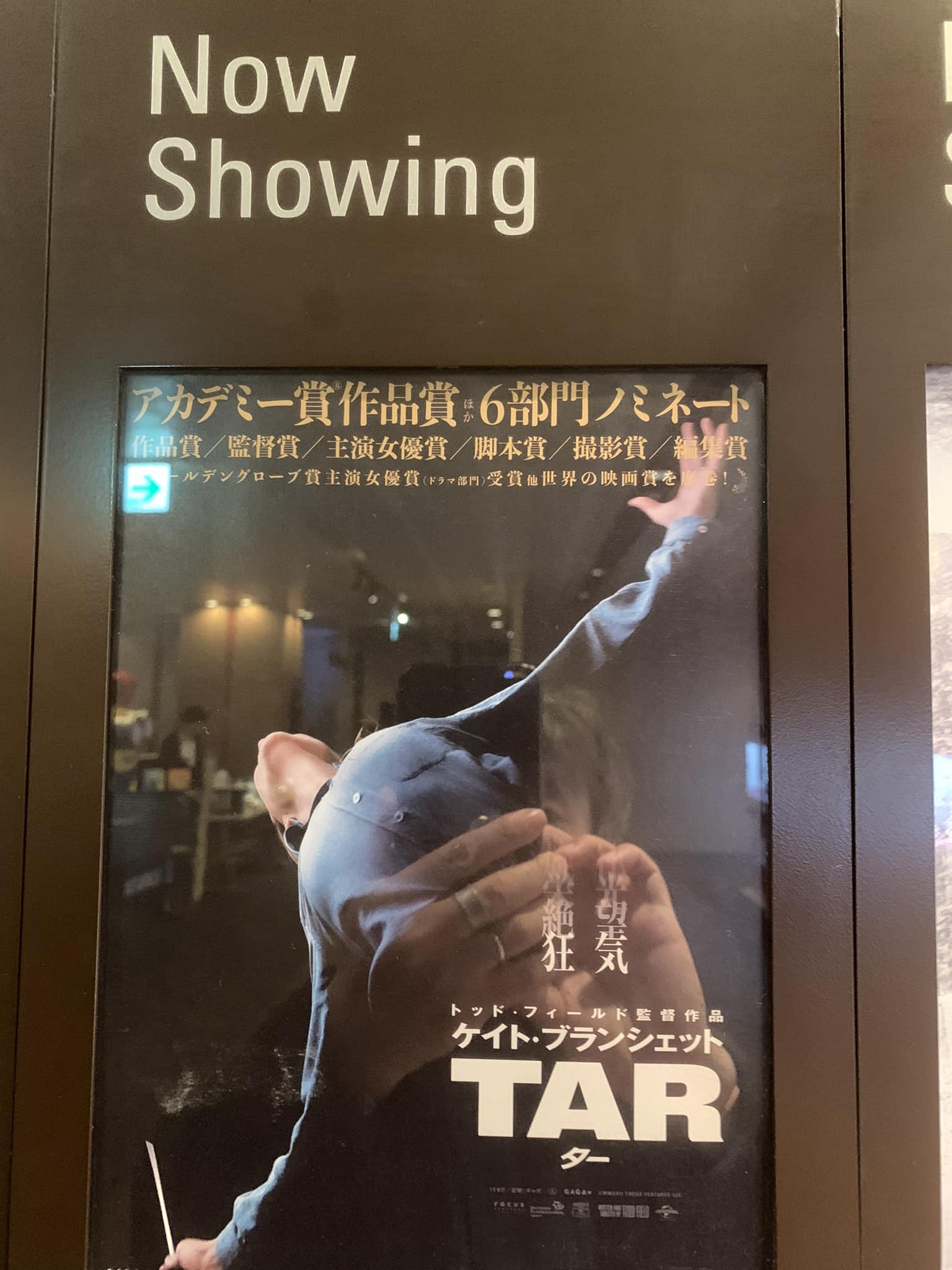
権威の崩壊と亡霊たち——映画『TÁR』が照らすクラシック音楽界の「いま」
◆ 業界の内部からしか見えない映画
映画『TÁR』(2022年、監督:トッド・フィールド)は、クラシック音楽界におけるジェンダー・権力・倫理・権威主義の問題を、きわめて“内側”から描いた稀有な作品である。劇中に登場する人物名や団体名、演奏家同士の微妙な緊張関係、音楽監督職の政治性、スキャンダルの処理、音源契約、果てはリハーサルの指示語まで——そのすべてが現実の業界を写し鏡のように反映している。
観る者を選ぶ作品である。だが、だからこそ、クラシック音楽に関わる者にとって『TÁR』は単なるフィクションではない。むしろ**「われわれの業界がすでに抱えている亡霊たち」を、明るみに出してしまった告発的作品**として読むことができる。
◆ 1. 「指揮者」という権威の構造
主人公リディア・ターは、著名な女性指揮者として、ベルリン・フィルの音楽監督を務め、マーラー全集録音を完結しようとしている。明らかに架空だが、彼女の人物造形には、ジェームズ・レヴァイン、シャルル・デュトワ、サイモン・ラトル、ダニエル・バレンボイムといった実在の大指揮者たちのエッセンスが詰め込まれている。
ターは音楽によって世界をコントロールできると信じている。リハーサルで音のニュアンスを精緻に調整し、オーケストラの一音に自分の思想を宿そうとする。“権威”としての指揮者像がそこにはある。
だが現実のクラシック音楽界では、この権威性こそが問われ始めている。2020年代以降、レヴァインやデュトワをはじめとする「カリスマ型」指揮者たちのスキャンダルが相次ぎ、巨匠崇拝の文化そのものが揺らいでいる。ターが象徴するのは、その終わりつつある“旧世界”の最後の生き残りなのだ。
◆ 2. キャンセルカルチャーと“見えない加害”
映画では、ターがかつて教え子に対して行った「倫理的にグレーな行為」が、SNSによって告発され、彼女の地位が崩壊していくさまが描かれる。だが観客には、何が真実で、何が虚構なのかは決して明示されない。
ここに描かれるのは、明確な「被害者」や「加害者」が不在のまま進行する、現代的な崩壊劇である。観客すら情報の断片しか与えられず、ターと同様に「何が起こっているのか分からない」まま追いつめられていく。
これはまさに、現代クラシック界における“失脚”の構造と重なる。レヴァイン事件、デュトワ事件、さらにはマルタ・アルゲリッチの擁護発言をめぐる議論など、正義と復讐、倫理と感情、芸術と制度がねじれ合う空間が実在する。映画はこの“ねじれ”を、主観カメラと不安定なサウンド、曖昧な時間軸で演出し、まさに「現在のクラシック界の恐怖」を視覚化している。
◆ 3. 権威崩壊後の世界:若者たちと新しい感性
映画後半、ターが若きチェリスト、オルガに惹かれていくくだりは象徴的だ。彼女はエルガーのチェロ協奏曲を愛しているが、ジャクリーヌ・デュプレの演奏は素晴らしいが、指揮者が誰かなど気にもしない。YouTubeで観て感動したから、それでいい。
これは**「名盤」「巨匠」文化の終焉**を意味している。若い世代にとって、クラシック音楽は「権威に従って聴くもの」ではなく、「自分の感性で楽しむもの」なのだ。ターはそれを理解できない。そして、その理解不能こそが、彼女を時代から切り離していく。
現実のクラシック界も、SpotifyやYouTubeを通じた「演奏単位の消費」や、ジェンダー・ダイバーシティの再構築、若手音楽家の台頭などにより、古い秩序の更新を迫られている。『TÁR』は、この変化の象徴を、ターの“理解不能な挫折”という形で描いている。
◆ 4. クラシック音楽界にとって『TÁR』とは何か?
この映画が本当に描いているのは、「クラシック音楽が今、どこからどこへ向かっているのか」である。
カリスマ指揮者の終焉
音楽を武器にする者の倫理的危うさ
SNS時代の権力の脆弱性
感性中心主義と若者の価値観
巨匠崇拝の解体と、個の再構築
クラシック音楽界が長らく抱えてきた構造的問題が、ターという虚構の人物を通してあぶり出されている。これはただのサイコドラマではない。「業界の予言」なのだ。
◆ 結語:亡霊は、まだ消えていない
映画には“幽霊”めいた存在が何度か登場する。ターの周囲に現れる不可解な影や音は、彼女の罪悪感や抑圧された過去の象徴だが、同時にそれはクラシック音楽界そのものが抱える「未解決の問題」の暗喩でもある。
まだ成仏していない亡霊たち——それこそが『TÁR』の本質である。
そして我々がその亡霊を直視しない限り、クラシック音楽は、新しい時代に進むことができないのかもしれない。
『TÁR』における「不感情移入性」の美学──まともな人物の不在と観客の恐怖
トッド・フィールド監督による映画『TÁR』(2022)は、架空の女性指揮者リディア・ターの栄光と失墜を描きながら、クラシック音楽界における権力構造、ジェンダー、芸術と倫理の交差点を探る作品であると広く受け止められている。しかし、この作品のより根源的な不穏さは、主人公を含むすべての登場人物が「どこかおかしい」という点、すなわち、観客が感情移入可能な「まともな人物」が一人として存在しないという構造的設計にこそ潜んでいるのではないだろうか。
まず、表面的には善良あるいは合理的に見えるキャラクター――たとえば助手のフランチェスカ、家庭のパートナーであるシャロン、オーケストラの理事など――でさえも、権力に従属したり、倫理的中立性を装いながら自己保身を図ったりするなど、完全な共感対象とはなりえない要素を抱えている。このような人物設計は、単なる写実を超えて、ある種の寓意的構造を帯びていると考えられる。
若きチェリストの存在は、物語序盤では唯一「まともな」人物として描かれていた。だが、物語が進行するにつれ、その存在は不穏な気配を帯び、ターの主観において徐々に実在感を失っていく。ターが彼女の住居を訪れた場面では、家はもぬけの殻であり、彼女が実在していた証拠も消え失せている。すなわち、チェリストの存在は物理的なものではなく、ターの罪悪感や妄執の投影であった可能性が高い。
すなわち、フィールドはクラシック音楽界という制度的・権威的装置そのものを批評するために、あえて「まともな人間が一人もいない世界」を提示しているのではないか。この点において、本作はルイス・ブニュエル的なアイロニーや、カフカ的な不条理性を継承しており、音楽業界の「高貴さ」の裏に潜む倒錯や欺瞞を白日のもとにさらしている。
重要なのは、この構造が観客の「感情移入」という映画的体験の基盤を意図的に崩壊させている点である。通常のドラマ作品では、主人公がどれほど道徳的に問題があっても、観客は何らかの共感や理解の糸口を得ることができるよう設計されている。だが『TÁR』では、観客が最後まで寄り添えるキャラクターが皆無であるため、物語世界への没入自体が宙吊りにされる。この「誰にも感情移入できない」不気味さは、クラシック音楽という洗練された文化空間に対する観客の暗黙の期待(すなわち、そこに品格や理性があるはずだという幻想)を逆手に取る、強烈な心理的反転効果をもたらしている。
このような構造により、『TÁR』は単なる一人の芸術家の墜落譚ではなく、クラシック音楽界という制度の深層にある倫理的空洞を暴き出す作品となる。全てのキャラクターがどこか「おかしい」という事実は、「まともでいることが制度内では機能しない」ことの示唆であり、ひいては観客に対しても「あなたならこの世界でまともでいられるか?」という不気味な問いを突きつけてくる。これはあるいは「クラシック音楽業界なんてまともな人間はいない」という皮肉をオブラートに包んでいるのかもしれない。
『TÁR』の最大の異様さは、明確な倫理的基点が存在しない点にある。ターによる権力の濫用や不適切な関係性は暗示されるものの、それが法的・道徳的にどのように裁かれるのかは一切示されない。証拠も曖昧で、被害者の姿すら明示されないことで、観客は「何が悪で、誰が正しいのか」の判断を下せず、倫理的な座標軸を失ってしまう。
このような構造によって、観客は常に「宙吊り」にされた状態に置かれる。まるで、降りるタイミングのわからない絶叫マシンに乗せられているかのように、緊張と不安が持続する。これは現代社会における「正義」の不確実性を象徴しているともいえよう。
結論として、『TÁR』における「感情移入不可能性」は、単なる冷淡な人物造形ではなく、クラシック音楽界という崇高な制度そのものに向けられたアイロニカルな批評であり、観客の美学的・倫理的立場そのものを揺さぶる、きわめて現代的な不安の演出装置なのである。
ブルーレイ&DVD
映画『TÁR/ター』をホラー映画的観点から読み解く試み
映画『TÁR/ター』をホラー映画的観点から読み解く試みは、作中で描かれる知覚の不安定性や語りの信頼性の崩壊に踏み込むものであり、本作の核心に肉薄する。以下、そのホラー的手法と構造について段階的に考察。
1. ホラー映画的構造と『TÁR』の類似性
『TÁR』は形式上は伝記映画や音楽家ドラマの装いを持ちながら、演出手法や心理描写には典型的な心理ホラー/スローホラーの文法が埋め込まれている。以下にその特徴を列挙:
2. 「怪現象」の正体:亡霊の影
最も象徴的な“幽霊”は、自死した元学生**クリスタ・テイラー(Krista Taylor)**であろう。彼女はターの権威的振る舞いと情的搾取の犠牲となり、直接描写はないものの、以下の点から「見えない亡霊」として映画を支配している:
ターがメール削除等で彼女を業界から排除しようとした痕跡。
ターに届く謎のスコア・本の送り主、落書きなどの「ポルターガイスト」的現象。
SNSを通じたターへの匿名的復讐キャンペーン。
最終的にターが精神的に追い詰められていく過程。
これは**「罪の自覚が生んだ亡霊」=心理的な亡霊**とも読めるし、クラシックなホラー文法で言えば、「復讐する死者の怨霊」がターに取り憑いている構図だ。
3. チェリストの「家」=異界との通路
問題の若いチェリスト・オルガ(Olga)を追跡する場面は、本作中でも最も現実性が崩れる瞬間。彼女の「家」とされる場所は、壁がコンクリートで閉ざされ、水音が反響する地下空間=**まるで“黄泉の国”**のような描写。
この場面に説明はなく、オルガの生活の痕跡も存在しない。考えられる解釈:
ター自身の罪意識が見せた幻覚的体験(=マークやクリスタが“異界から呼んでいる”というメタファー)。
オルガそのものが実在しない存在(あるいはターの欲望が作り上げた虚像)。
「下水管的空間」=精神的堕落の比喩空間、ターが自ら招き寄せた「地獄」への導入部。
これはまさにホラー映画で登場する異界的ポケット空間の手法。『シャイニング』『ブラック・スワン』『ローズマリーの赤ちゃん』等に共通する、「登場人物の精神崩壊を視覚化する場」としての演出であり、解釈を曖昧にしたまま観客に“怖さ”を残している。
4. なぜホラー手法が用いられるのか?
これが最も重要な問いである。
結論:
ターというキャラクターの「権威と罪」と「孤立と崩壊」を、最も強く・深く描くために、ホラーというジャンルの視覚・音響的語彙が必要だった。
社会的権威者が「権力の乱用」によって破滅していく様を、リアルな描写(裁判や懲戒)ではなく、“因果応報”の物語様式=ホラー”で描く。
恐怖の主体が「外部にあるモンスター」ではなく、ター自身の内部=彼女の良心と罪意識にあること。
観客に「何が現実で何が幻覚か」を断言させないことで、権力者の主観がいかに歪んでいるか/世界と乖離しているかを表現する。
5. 終末の“異世界”:逃避か、裁きか?
最後の東南アジアでのゲーム音楽指揮のシーン。ターは子供たちの観客に向かって指揮棒を振っている。観客の仮面と会場の異様な熱気、オーケストラの構成など、現実とファンタジーの境界が完全に曖昧である。
ここに至って、『TÁR』はホラーの一変種である**「地獄譚」**の系譜に入りこんでいる。
これはターの芸術家としての死後の煉獄であり、彼女が「理想を捨て去った対価として生き残る場所」。
あるいは、彼女自身が「死んだ」あと、この地獄に堕ちたのではないかという暗示も読み取れる。
結語
:
『TÁR』は「モンスターを作る社会」「モンスターになった個人」「それに取り憑く亡霊」そして「芸術の意味の崩壊」といったテーマを、ホラー的文法(音・空間・幻視)を用いて描いた現代の心理怪談である。
だからこそ、説明されない怖さ、見えない亡霊、夢のような空間が不可欠だったのであろう。
『TÁR』における「回収されない伏線」の恐怖構造について
映画『TÁR』が観客に与える最大の不安要素は、「伏線が回収されない」という構造的手法にある。本作においては、観客の理解を促すための説明や背景描写が意図的に欠落しており、その「不親切さ」こそが、独特の心理的恐怖を形成している。
1.MCU的構造との対比
現代の娯楽映画、特にマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)に代表される作品群は、物語の中に散りばめられた伏線を最終的にすべて回収し、観客に明確な因果関係とカタルシスを提供する。観客は「理解」することで快感を得る構造に慣れている。
一方『TÁR』は、この「理解可能性」そのものを裏切る。提示された多くの要素は説明されず、放置され、物語からの明確な答えを得られないまま観客は映画を終えることになる。
本作では、典型的な物語構造、すなわち伏線の提示とその回収、善悪の明示、カタルシスの提供といった「物語的サービス精神」が意図的に回避されている。これは、公開当時社会現象化していたMCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)のような、消費型エンタメ映画への明確なアンチテーゼである。
観客は情報を与えられるが、導かれることはない。答えは用意されておらず、むしろ観客自身に判断を委ねるという構造によって、「理解できない不安」と「腑に落ちない感覚」が意図的に設計されている。これは映画が提示する世界が、そもそも曖昧で不確かなものであるという主張の現れである。
2.主な「未回収」の要素
本作には多くの未回収要素が存在する。たとえば、作中で一度だけ言及される「デュトワの事件」。それが何であるのかは最後まで明かされない。また、リディアの部屋の隅に立つ人影、遠くに聞こえる声、誰かの存在を暗示するような物音など、心霊現象めいた描写も随所に現れるが、それらの正体についても語られない。「今、部屋の隅に誰か人が立っていたよね?」しかし、その後それは説明されずに終わるのだ?こんな不安なことはない。
さらに、劇中に散見されるクラシック音楽界特有の専門用語や実在の人物の言及も、観客の知識の有無に関係なく、解説を伴わずに放たれる。こうした要素は、映画にリアリティと密度を加える一方で、観客を「知識の不足」へと追い込み、不安を煽る装置として機能している。
3.心理的効果としての「不安の放置」
人間は「意味を与える」ことにより安心を得る生き物である。ゆえに、提示された情報が解明されないまま放置されると、脳は無意識に「補完」しようとし、精神的な疲労を生じさせる。これは『TÁR』の戦略的効果である。
作中において、観客が「これはリディアの妄想なのか?現実なのか?」と揺さぶられ続けるのも、すべてはこの「不確定性の持続」によるものだ。伏線が回収されないことで、リディアの内面世界が現実世界に浸食してくるさまを観客もまた体験することになる。
4.「未解決」の演出美学
『TÁR』の演出は、デヴィッド・リンチやスタンリー・キューブリックといった作家たちの手法とも共鳴している。とりわけ『シャイニング』のように、「説明されないこと」自体が恐怖の源泉として機能する構造は、本作においても顕著である。
リディア・ターの精神的崩壊や自己認識の揺らぎは、映画の構造と完全に呼応しており、意味の空白こそが主題的な役割を担っている。伏線の未回収は単なる情報の欠落ではなく、作品全体の構造的選択であり、観客に「知的恐怖」を植え付けるための美学なのである。
結論:恐怖は「意味の欠如」から生まれる
『TÁR』は、あらゆる物語的・心理的・音響的・演出的伏線を提示しつつ、それらの多くを意図的に回収しないという方法によって、観客に「意味がわからない」という根源的恐怖を与える。
この恐怖は、通常のホラー映画における外的脅威ではなく、「理解できない」という内的脅威である。観客の認知的不協和を巧みに利用した構造は、極めて知的であり、なおかつ根深い不安を残す。
本作は、物語の完結や整合性といった従来の映画的快楽とは真逆のアプローチによって、観る者を物語世界の渦に巻き込む。まさに、「回収されない伏線」こそが『TÁR』の恐怖そのものなのである。
呪物としてのエルガー:音楽が物語を侵蝕する
物語の終盤で重要な役割を果たすのが、エルガーの《チェロ協奏曲》である。この曲は、第一次世界大戦後の深い喪失感と哀惜の念をたたえた作品であり、エルガーの音楽の中でも最も内省的で陰影に富むものとされる。
本作ではこの曲が、「呪物」として機能している。ターがこの協奏曲に取り組む過程で、彼女の精神的崩壊が進行するという描写は、まるでこの音楽自体が人間の内面を蝕むような「霊的な力」を持っているかのようである。すなわち、音楽が「超自然的な力」として作用するという演出であり、ターが直面する崩壊や幻覚は、音楽によって引き起こされたものでもある。
❖ 結語:ターは何を見ていたのか
『TÁR』は、現実と妄想、正義と悪、権力と芸術といったあらゆる二項対立を意図的に曖昧にすることで、観客に「解釈せざるを得ない」構造を強いる映画である。ターは、自らの野心と栄光の頂点にあって、同時にすでに崩壊していた。彼女の見るもの、聞くもの、触れるものは、いずれも現実であるかの保証はなく、すべてが彼女の内面世界の投影であった可能性すらある。
この映画における「音楽」とは、もはや表現手段ではなく、霊的媒介であり、人間の深層に触れる呪術的作用を持つものとして描かれている。エルガーのチェロ協奏曲がその象徴として使われることは、まさに音楽の「光と影」の両面性を最大限に活用した表現である。
『TÁR』を「ホラー映画」として読み解く際、現在の映画の構造(ターの視点=主観)をひっくり返し、第三者の視点=傍観者の目線から描いたらどうなるか、という問いは、この作品の持つ「潜在的ジャンル変換力」の核心に迫る。
以下に、この「もし『TÁR』が純粋なホラー映画だったら?」という仮定に基づいて、その演出や物語構造の変化を詳細に掘り下げる。
◉ 1. ジャンル変換の仮定:ター主観から「第三者視点」への切り替え
現在の『TÁR』は、ターの視線、あるいは彼女の記憶・妄想・幻想と現実が混交した「不確かな主観」に基づいて語られている。ゆえに、観客には「何が事実か」が提示されず、ターの視点に追随せざるを得ない構造となっている。
しかしこれを、クラシックなホラー映画の構造――つまり「亡霊に呪われる加害者」を外部から観察する立場――で描いたとすれば、以下のような変化が生じる。
◉ 2. ホラー構造における「第三者」=目撃者・媒介者の存在
ホラー映画において、超常現象を知覚し、観客の共感を担う役割を果たすのは「目撃者」の立場にある登場人物である。この人物は以下のような立ち位置を取る:
元被害者の友人/家族(例:死んだ若者=クリスタの姉妹や恋人など)
新しくターの周囲に雇われたスタッフ(秘書やアシスタント)
単なる部外者だが超常的現象を察知する能力を持つ人物(例:霊媒師的存在)
この第三者の視点から見ると、ターの身の回りに起こる異変は徐々にエスカレートしていく。
▷ 例:演出案(ホラー文法)
夜中にひとりで指揮スコアをチェックするターの背後で、廊下を横切る黒い影。
モニター越しに録音映像をチェックしていた助手が、「ターの背後に誰かが立っていた」ことを発見。
アーカイブ室で誰もいないはずの棚からスコアが落ちる。拾い上げると、血で書かれたメッセージが見つかる。
ターが眠る間、壁の中からかすかな弦の響き。これはクリスタの弾いていたフレーズ。
このような演出の累積によって、「ターが呪われている」ことが第三者視点で明示されていく。
◉ 3. 呪いの構造と亡霊の描き方
「死者が生者に取り憑く」構造は、古典的なホラー(『リング』『オーメン』『ゴースト・ストーリー』など)と共通する。ここで重要なのは、ター自身が気づいていない、もしくは気づいても否認しているという二重性である。
観客には「霊」が見えているが、ターは見えないふりをする。
周囲の人物(例:アシスタント)は「何かおかしい」と気づき、観客と共に恐怖を共有する。
音楽の演奏中にターだけが聞こえるはずのない声を聴き、指揮が破綻する。
使用していないスタジオから音がする。行ってみると、スコアが無造作にばら撒かれている。
◉ 4. 結末:呪いの終焉か、永遠の輪廻か
ホラー映画には二通りの終幕がある:
a. 呪いの終焉(カタルシス型)
第三者が犠牲となりながらも、霊の正体を解明し、ターに真実を突きつけることで、ターが自らの罪を認め、霊が成仏。ターは精神的に崩壊するが、物語は終結する。
b. 呪いの拡散(ループ型)
誰も霊の正体にたどり着けず、ターは完全に破滅。だが次の被害者候補(指揮助手や新たなチェリスト)に呪いが乗り移る。演奏とともに霊は甦る。
このパターンでは、エルガーの《チェロ協奏曲》が「呪われた楽曲」として映画を貫く。すなわち、「この曲を演奏するたびに霊が蘇る」という構造であり、音楽が霊的媒介物=呪物として描かれる。
◉ 5. 映像美とジャンル融合の可能性
『TÁR』の美術・音響設計はすでにホラー的要素を含んでいる:
無音や環境音(耳鳴り)の強調
シャープで冷たい美術設計(ベルリンのアパートメント、スタジオの無機質さ)
光のコントラスト、長回しの異常な緊張感
これらを強化し、完全なホラー文法へ移行した場合、映画は『ブラック・スワン』『ヘレディタリー』『ローズマリーの赤ちゃん』のような「心理=オカルトホラー」の名作群と並ぶことになる。
◉ 結語:『TÁR』はすでにホラーである
この仮想演出の提案を通じて明らかになるのは、『TÁR』は構造的にすでにホラーとして成立しているという事実である。視点の選択によって「芸術映画」と「ホラー映画」は容易に変換可能であり、その境界が曖昧であることこそがこの映画の本質なのである。
『TÁR』における「回収されない伏線」の恐怖構造について
映画『TÁR』が観客に与える最大の不安要素は、「伏線が回収されない」という構造的手法にある。本作においては、観客の理解を促すための説明や背景描写が意図的に欠落しており、その「不親切さ」こそが、独特の心理的恐怖を形成している。
1.MCU的構造との対比
現代の娯楽映画、特にマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)に代表される作品群は、物語の中に散りばめられた伏線を最終的にすべて回収し、観客に明確な因果関係とカタルシスを提供する。観客は「理解」することで快感を得る構造に慣れている。
一方『TÁR』は、この「理解可能性」そのものを裏切る。提示された多くの要素は説明されず、放置され、物語からの明確な答えを得られないまま観客は映画を終えることになる。
2.主な「未回収」の要素
本作には多くの未回収要素が存在する。たとえば、作中で一度だけ言及される「デュトワの事件」。それが何であるのかは最後まで明かされない。また、リディアの部屋の隅に立つ人影、遠くに聞こえる声、誰かの存在を暗示するような物音など、心霊現象めいた描写も随所に現れるが、それらの正体についても語られない。「今、部屋の隅に誰か人が立っていたよね?」しかし、その後それは説明されずに終わるのだ?こんな不安なことはない。
さらに、劇中に散見されるクラシック音楽界特有の専門用語や実在の人物の言及も、観客の知識の有無に関係なく、解説を伴わずに放たれる。こうした要素は、映画にリアリティと密度を加える一方で、観客を「知識の不足」へと追い込み、不安を煽る装置として機能している。
3.心理的効果としての「不安の放置」
人間は「意味を与える」ことにより安心を得る生き物である。ゆえに、提示された情報が解明されないまま放置されると、脳は無意識に「補完」しようとし、精神的な疲労を生じさせる。これは『TÁR』の戦略的効果である。
作中において、観客が「これはリディアの妄想なのか?現実なのか?」と揺さぶられ続けるのも、すべてはこの「不確定性の持続」によるものだ。伏線が回収されないことで、リディアの内面世界が現実世界に浸食してくるさまを観客もまた体験することになる。
4.「未解決」の演出美学
『TÁR』の演出は、デヴィッド・リンチやスタンリー・キューブリックといった作家たちの手法とも共鳴している。とりわけ『シャイニング』のように、「説明されないこと」自体が恐怖の源泉として機能する構造は、本作においても顕著である。
リディア・ターの精神的崩壊や自己認識の揺らぎは、映画の構造と完全に呼応しており、意味の空白こそが主題的な役割を担っている。伏線の未回収は単なる情報の欠落ではなく、作品全体の構造的選択であり、観客に「知的恐怖」を植え付けるための美学なのである。
結論:恐怖は「意味の欠如」から生まれる
『TÁR』は、あらゆる物語的・心理的・音響的・演出的伏線を提示しつつ、それらの多くを意図的に回収しないという方法によって、観客に「意味がわからない」という根源的恐怖を与える。
この恐怖は、通常のホラー映画における外的脅威ではなく、「理解できない」という内的脅威である。観客の認知的不協和を巧みに利用した構造は、極めて知的であり、なおかつ根深い不安を残す。
本作は、物語の完結や整合性といった従来の映画的快楽とは真逆のアプローチによって、観る者を物語世界の渦に巻き込む。まさに、「回収されない伏線」こそが『TÁR』の恐怖そのものなのである。