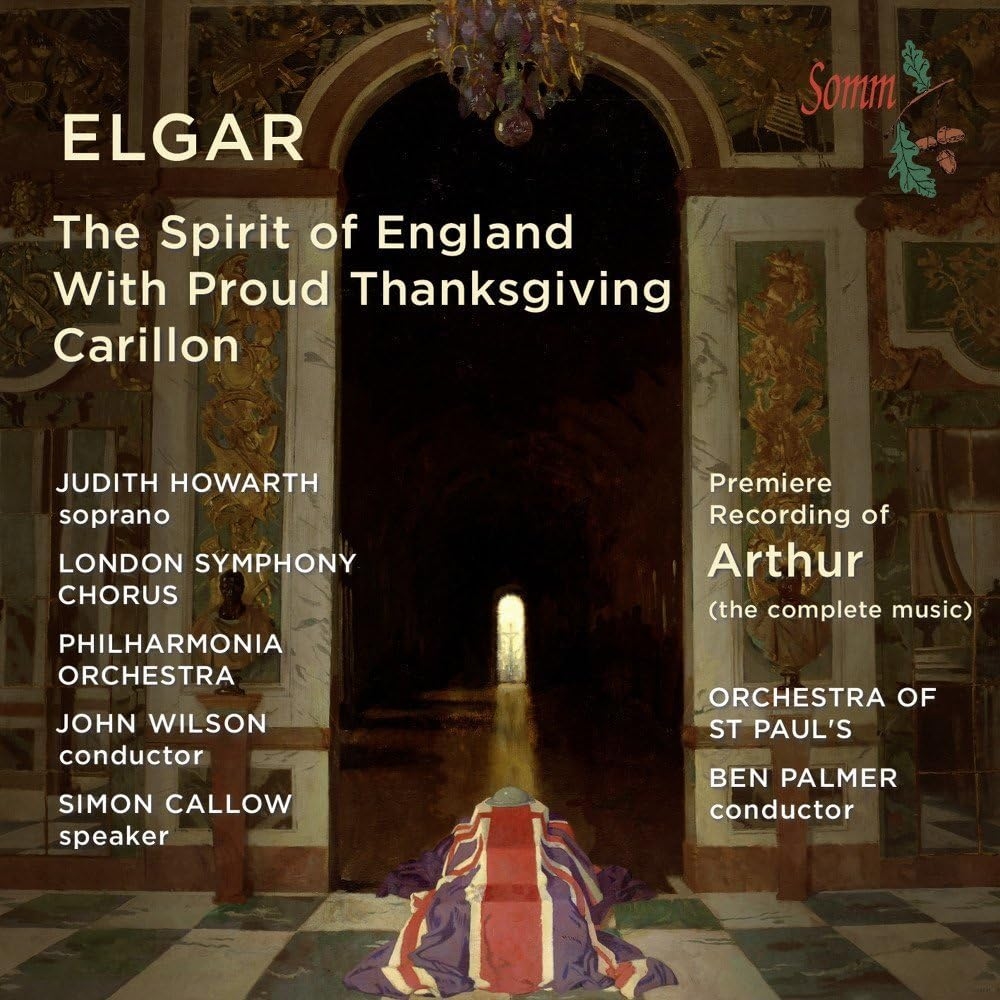《The Spirit of England》における音楽的儀式性の諸相
―各楽章の構造的・象徴的分析を通じて―
はじめに
エルガーの《The Spirit of England》は、第一次世界大戦の戦没者を追悼する目的で作曲された3つの歌曲(ないしオラトリオ的楽章)から成る作品である。詩はローレンス・ビニョンによる愛国的かつ崇高な英霊への賛歌であり、全体として一種の宗教的・儀式的性格を帯びている。エルガーがかつて『The Dream of Gerontius』『The Apostles』『The Kingdom』において展開したオラトリオ的・宗教劇的世界と接続する構造が、本作にも内在している。以下、各楽章における音楽的儀式性を検証する。
第1楽章「The Fourth of August」(1914年8月4日)
この楽章は、イギリスが第一次世界大戦に参戦した日を主題としている。序奏部は荘厳な和音によって始まり、まるで国家的な祭儀の開幕を告げるファンファーレのように響く。拍節感の明確な構築、トゥッティの重厚な響きは、英国王室の式典を連想させるバロック的荘厳性と、エルガー自身の行進曲様式(特に『威風堂々』)に通じる。
音楽的には、この冒頭は明確に儀式の「開会宣言」として機能しており、以後に続く音楽は「国家の霊魂(spirit)」の召喚と捉えることができる。すなわち、「英国精神」という抽象的概念を音楽的実体として呼び起こす呪術的行為である。
中間部において提示されるソプラノの旋律線は、柔らかくも儀礼的であり、特定個人ではなく「国民一般」の悲哀と決意を象徴する。「When the men that were children heard the call of the Motherland」という句に付された旋律の処理は、まさに聖体拝領における叙唱に類似した音楽言語を用いている。
楽章の終結は、初めの荘厳さに回帰しつつ、より抑制された終止を迎える。この反復によって、形式的円環が作られ、音楽儀式としての完結性を示している。
第2楽章「To Women」
この楽章は、戦争によって愛する者を失った女性たちへの追悼と称揚の意味を持つ。全体は内省的で、祈りのような響きに満ちており、宗教儀式としての「ミサの奉献唱」に類する性格を持つ。
冒頭から提示される弦のテクスチャーは、透明でありながら神秘的な響きを作り出す。この部分は、まるで儀式における香の立ち上る様を音で描写するかのようである。詩の内容もまた、犠牲と贖罪の文脈に深く関わっており、聖母マリアの受難に重ねるような構図が暗示されている。
声楽部における旋律の処理は、「アジリタ」や「カンタービレ」といった標示のないにもかかわらず、明らかに受難曲的様式を踏襲しており、特に「You who have wept」の部分は、マタイ受難曲におけるコラール様式に通ずる。
後半における強奏部の導入は、感情の爆発ではなく、むしろ集団的な嘆き、典礼的な嘆願の形式をとる。音楽的にはレクイエムの「Dies Irae」の陰影を反映しており、この構造が楽章全体を宗教的かつ儀式的に支えている。
第3楽章「For the Fallen」
最終楽章は、詩的にも音楽的にも《The Spirit of England》全体の頂点であり、最も明確な儀式的性格を有する楽章である。冒頭の重厚な主題提示は、まさに「葬送行進曲」の音型を内包しつつ、神聖なプロセッション(行列)の音楽として構成されている。
特に注目すべきは、「They shall grow not old」の部分である。ここでエルガーは、単なる哀悼の詩句を、儀式の中核たる「リタニア」(連祷)として扱い、反復と拡大によって崇高な形式にまで高めている。各反復ごとに音楽は厚みを増し、最終的には合唱とオーケストラが一体となって、まるで「神の声」としての響きを獲得する。
この反復構造は、グレゴリオ聖歌や東方典礼の応答詩篇唱に共通する音楽構造であり、ここにエルガーの宗教音楽家としての意識が顕著に現れる。「We will remember them」のフレーズは、音楽的には応答句(versicle and response)として処理され、聴衆・演奏者・英霊との三者的対話を成立させる。
終結部に至る過程では、管弦楽が荘厳な終止を作り出すが、それは単なる音楽的カタルシスではなく、まるで国家の記憶を封じ込めるかのような「終止儀礼」として機能している。これにより、《The Spirit of England》全体が、イングランドの英霊を弔う音楽的ミサ、すなわち「国家的レクイエム」として完結するのである。
結語
《The Spirit of England》は、戦争と死を題材にしつつも、単なる情緒的追悼を超えた、極めて儀式的・宗教的な構造を持つ音楽作品である。各楽章が持つ形式的・象徴的処理は、エルガーが《ゲロンティアスの夢》以降深化させてきた「音楽による儀礼(musicalliturgy)」の最終形態の一つとも言えるだろう。本作品における「儀式性」は、作曲家エルガーにとって、時代と死を超えてイングランドの精神を音楽として現出させるための、最も純粋な言語であったのである。