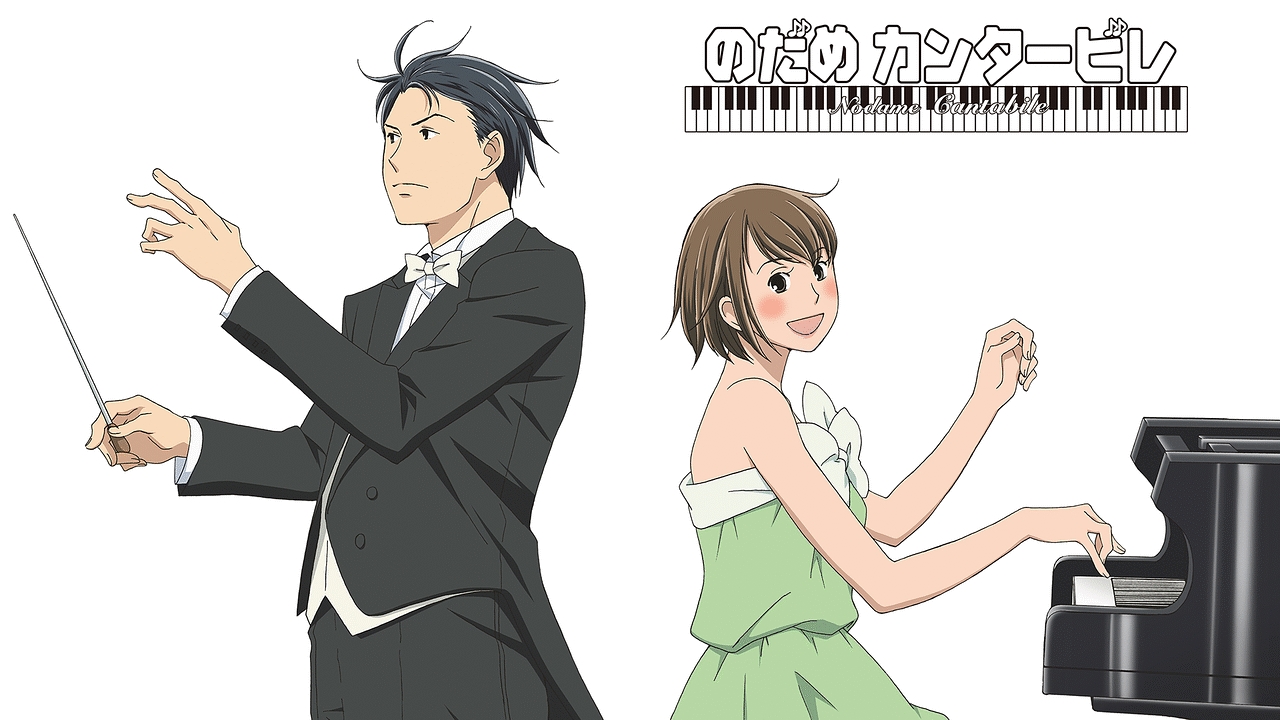のだめカンタービレでのエルガー
のだめカンタービレでエルガーのヴァイオリンソナタが紹介されたこの場面、たしかに名シーンだけど、我々エルガリアンからすると突っ込みたくなる部分がある。
ここに出てくるお父さん、エルガーの作品で、威風堂々、愛の挨拶、交響曲1から3番、ゲロンティアスの夢、弦楽四重奏などを知っているのにヴァイオリンソナタを知らない・・・・。
そんなヤツいるわけない。どんな聞き方してんの?という感じ・・・。
まだ、純粋にエルガーの作品じゃない交響曲3番を知らないってのならわかるけど。
弦四を知っててソナタ知らない・・・ありえない。ほぼ同じ時期に作曲された作品だ。
ゲロンティアスの夢まで名前出しているのにネ。
なんかそれが面白かったので。
のだめカンタービレとエルガーのヴァイオリン・ソナタ―“作劇”と“リアリティ”の狭間で
2000年代に一世を風靡したクラシック音楽を題材とする漫画/ドラマ/アニメ『のだめカンタービレ』。その作中で取り上げられるクラシック作品群は、既存の名曲の再発見やマニア心をくすぐる選曲で多くの音楽ファンを魅了した。その中でも、とりわけ異彩を放つのが、**エルガーの《ヴァイオリン・ソナタ ホ短調》**が紹介される場面である。
本作におけるこのソナタの登場は、「お父さん」が「初めて聴いて心を動かされた」と語る印象的なシーンによって印象づけられている。ドラマ的な演出としては非常に効果的であり、またこの作品の持つ静謐な美しさと深い叙情性が、キャラクターの心理描写とよく呼応している。
しかし――エルガー愛好家(エルガリアン)の視点から見ると、この設定にはいささか不自然な点がある。
エルガー入門者なのか、玄人なのか?
「お父さん」は、台詞中で「エルガーの作品は《威風堂々》《愛の挨拶》《交響曲第1〜3番》《ゲロンティアスの夢》《弦楽四重奏》などを知っている」と発言する。これはかなり深い知識だ。
とりわけ、《ゲロンティアスの夢》に言及する時点で、ただの通りすがりのクラシック愛好家ではなく、相当に探求的な聴き手であることがわかる。オラトリオ作品にまで手を伸ばす聴衆は限られており、英国音楽に興味がなければなかなか到達しない領域だ。
ところが――彼はヴァイオリン・ソナタを「知らなかった」と語る。
これはやや奇妙である。
というのも、エルガーが晩年に取り組んだ**室内楽三部作(ヴァイオリン・ソナタ、弦楽四重奏曲、ピアノ五重奏曲)**は、彼の創作において密接に結びついた作品群であり、いずれか一つを知れば自然に他の二つにも出会う可能性が高い。とりわけ弦楽四重奏曲を聴いておきながら、ヴァイオリン・ソナタにはまったく気づかないというのは、情報の取り方として不自然なのだ。
脚本上の「仕掛け」としての選曲
もちろん、この描写は**「ヴァイオリン・ソナタを父が“初めて聴いて涙した”」というドラマ的なカタルシス**を目的として挿入されている。ストーリー上、重要なのは「知られていなかった名曲が、人を動かす力を持っている」というメッセージだ。
このため、脚本上は“知られていない曲”であることが重要視され、逆説的に《ヴァイオリン・ソナタ》がその役割を担わされたと考えられる。
だが――そうだとしても、《ゲロンティアスの夢》や《弦楽四重奏曲》を出してくるほどのリスナーが、《ヴァイオリン・ソナタ》をまったく知らないというのは、リアリティに若干の綻びを生む。むしろ、まったくのクラシック初心者が、子どもを通してエルガーに触れていくという設定にした方が、リアリズムとしては自然だったかもしれない。
それでも、名シーンであることに変わりはない
とはいえ、エルガーのソナタがテレビドラマでここまで美しく扱われた事実は、特筆に値する。
この楽章の演奏が、家族の心理的距離を縮め、家族としての回復を象徴するように描かれたのは、エルガーの晩年の作品の「静かな回想性」「苦みを含んだ美しさ」を的確に理解した選曲と言える。
エルガリアンにとっては「そんなヤツおらへんやろ」案件であると同時に――多くの視聴者にこの隠れた名曲を紹介したという点で、功績も大きいのである。