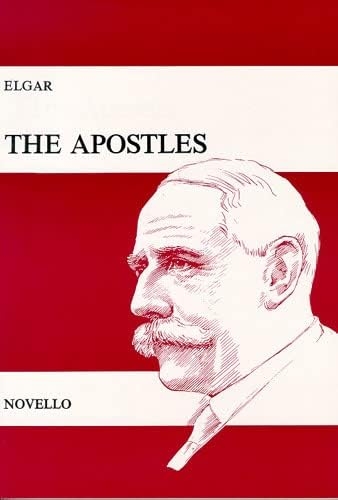《The Apostles》作品49
エルガーのオラトリオ《The Apostles》(1903)は、《The Dream of Gerontius》《TheKingdom》とともに、キリスト教世界における魂の救済、啓示、共同体の形成という主題を音楽的に探求した作品である。エルガー自身は、これらを連関する壮大な構想のもとに構成しており、《The Apostles》はその導入部として、選ばれし者たちがいかにして使命を託され、聖霊によって変容していくかを描く。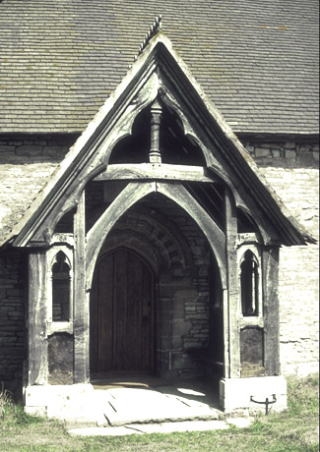
この作品において特筆すべきは、「12」という象徴的な数字の扱いである。エルガーは《The Kingdom》や未完の《The Last Judgement》に至るまで、12使徒という構成原理を儀式的・構造的に強く意識している。12は旧約のイスラエル12部族に対応し、新約においては新しい神の民の礎石である。彼はこの数字を単なる聖書的な事実としてではなく、音楽構造と演出上の対位法的な原理としても活用している。
冒頭「夜(The Spirit of the Lord)」におけるファンファーレ的動機と神秘的なハーモニーは、明らかに《ゲロンティアスの夢》や《The Kingdom》の諸動機と共通の「儀式性」を共有している。特に冒頭の旋律は、ショファール(shofar)に由来すると思しき、古代的で告知的な音型であり、後続する《The Kingdom》の冒頭とも音型的な関連をもつ。これにより、エルガーは時間を超えた神の計画の序章を印象づけている。
《使徒たち》の全体構造は2部に分かれ、第一部は弟子たちの召命とユダの物語を中心とし、第二部は復活後の使徒たちの変容と布教を描く。エルガーはしばしば語っていたように、彼の関心は「英雄たちの行動」よりも「内的な精神的変容」にあった。そのため、音楽はしばしば劇的なクライマックスを回避し、むしろ内省的で黙示的な性格を帯びる。
中でもユダの描写は、従来のキリスト教音楽における「裏切者」としての固定観念を超え、人間の弱さと苦悩、そして救済の可能性という主題へと昇華されている。ユダのアリア「Lord, is it I?」においては、彼の良心の葛藤と哀しみが濃密な和声進行と陰影あるオーケストレーションで描かれ、彼の存在が単なる裏切りではなく、物語全体の構造を支える「影」として機能する。
また、《The Apostles》のクライマックスに位置づけられる「五旬節(Pentecost)」の場面では、聖霊降臨の力がトロンバ・グランデ(大型トランペット)によって象徴され、古代ユダヤ教のラッパ=ショファールの音響的再現とも解釈可能である。エルガーはこのようにして、19世紀的ロマン主義の枠を超え、古代宗教儀式の音響イメージを西欧オラトリオ形式の中に接続しようとした。
彼がこの作品で試みたのは、「神話的時間」における啓示の再現である。聴衆は、登場人物の心理を追体験するというより、荘厳な儀式の目撃者・参列者として位置づけられる。これは《ゲロンティアスの夢》における三重構造──すなわちエンジェル、アニマ、アニミ・クリスティの三位──とも通底しており、エルガーの宗教音楽が根底に持つ「儀式劇」としての性格を端的に表している。
結語として、《The Apostles》は単なる聖書物語の音楽化にとどまらず、「呼びかけと応答」「裏切りと贖い」「沈黙と顕現」といった宗教的二項対立の構造を音楽的に具現化した作品である。それはエルガーが生涯を通じて探求した「見えざるものの音楽化」、すなわち神的真理と人間の魂との交錯の音響的記録であると言える。
《The Apostles》パート別分析および演奏解釈上の注目点
序章:「The Spirit of the Lord is upon Me」
この冒頭合唱は作品全体のプロローグとして機能し、神の霊が人間に降りて使命を授けるという構想を音楽的に予告する。柔らかい弦の和声の中から現れる主旋律は、聖霊(Holy Spirit)を象徴する「下降音型」と「広がる分散和音」から成り、終盤の《The Kingdom》とも共通する動機的基層を形成している。
演奏解釈上の注目点:
弦楽群は「音響のヴェール」のように扱われるべきであり、テキストに対応する和声変化を細やかに描く必要がある。オルガンが加わる箇所では、響きが硬化しないよう、教会空間のような残響を意識したタッチが求められる。
第1場:「The Calling of the Apostles」
イエスが弟子たちを呼び寄せる場面であるが、演出的・音楽的にはむしろ「自然界の神秘」として描かれる。夜明けの描写(弦楽のトレモロとホルンの模倣)は、マーラー的な交響的手法に通じる部分もあり、光が差し始める音響として特筆される。
動機分析:
ここでは「召命の動機」(下降4度音程と長2度の跳躍を含む)が繰り返し現れ、主に木管とホルンで提示される。この動機は作品全体を貫く「選び」の象徴である。
演奏解釈上の注目点:
語りと合唱の間のバランスに注意を要する。特に福音書の地の文(narration)と、神の呼びかけの違いを音色と発音の明確な対比で表現する必要がある。
第2場:「By the Wayside」
弟子たちの内的独白に相当するこの場面では、宗教的覚醒が始まる。バリトン独唱による「私たちは何を求めるのか」という問いは、後の《The Kingdom》におけるペテロの内的成長とパラレルである。
演奏解釈上の注目点:
ソリストには、朗唱的な表現と旋律的なレガートの両立が求められる。内省的なフレージングが鍵であり、過度な感情移入は避け、霊的な透明さを保つべきである。
第3場:「By the Sea of Galilee」
ペテロとヨハネの主題によって構成される二重唱であるが、実質的にはペテロの心理描写が主軸である。旋律はやや民謡的でありながら、調性の曖昧さが弟子たちの迷いを表している。
動機的特徴:
「魚をとる」場面において使用されるアルペジオ音型は、《The Kingdom》における「水をくむ」場面の動機と関連する。
演奏解釈上の注目点:
ペテロ役には、語りの明瞭さと苦悩の内在化が求められ、声量ではなく内的緊張によって場面を牽引すべきである。
第4場:「The Betrayal」
ユダの物語の核心部分であり、作品中もっとも劇的かつ心理的に深い場面である。ユダは、単なる「裏切者」ではなく、神の計画の一環として内的葛藤を抱えた「苦悩する存在」として描かれる。
音楽的特徴:
ユダの主題は、半音階的下行と不安定な調性を特徴とし、ワーグナーの《トリスタン》に通じる内破的和声を形成する。
演奏解釈上の注目点:
ユダ役のバス・バリトンには、内的焦燥と諦念の音色的表現が求められる。特に「It was night」という語句における声の沈みとオーケストラの沈黙との同期が極めて重要である。
第5場:「Golgotha(カルヴァリオ)」
十字架刑の場面だが、直接的な苦痛よりも「宗教劇としての象徴性」に重きが置かれている。合唱はモブ(群衆)ではなく、宇宙的なコロスとして配されている点が独特である。
動機分析:
ここでの「犠牲の動機」は、《Gerontius》の「Sanctus fortis」や、《The Kingdom》の「洗礼の動機」と同系の素材から派生している。
演奏解釈上の注目点:
音量的クライマックスに頼らず、「間」と「沈黙」を活用した演出が重要である。合唱は怒声ではなく、儀式における「宣言」として統一されたフレージングが望まれる。
第6場:「At the Sepulchre」および「The Ascension」
キリストの復活と昇天を描く終章であり、形式的には古典的カンタータを踏襲しつつも、音響的には未来的な透明さを備えている。
動機分析:
ここでは冒頭の「聖霊の動機」が変奏され、金管群によって高揚感を伴って再提示される。これは《The Kingdom》冒頭の「新しい秩序」へとつながる。
演奏解釈上の注目点:
合唱には「地の合唱」から「天の合唱」へと質感を変化させる表現力が必要であり、特にピアニッシモでの音程感、透明度が重要である。指揮者はテンポの自然な拡張と残響の利用を的確に行うべきである。
結語:演奏上の全体的視点
《The Apostles》は、外面的なドラマ以上に「霊的現象の音楽的具象化」に重きを置いた作品である。そのため、演奏者にはリタルダンドやアッチェレランドなどの表面的な操作以上に、「儀式空間としての音場形成」が求められる。これは、単に正確な演奏技術だけではなく、スコア全体に流れる宗教的象徴の理解と内面化を必要とする。
全体構成と物語の流れ
《使徒たち》は二部構成で、各部は複数の場面から成る。物語は、使徒の召命から始まり、マグダラのマリアとユダの内面に焦点を当て、キリストの受難、復活、昇天へと進む。
第1部
序章:夜明け前の静けさの中、キリストが祈る場面から始まる。ここで主要な動機が提示される。
使徒の召命:キリストが使徒たちを召し出す場面。ショファール(ユダヤの角笛)の音が印象的である。
山上の垂訓:キリストの教えが語られ、使徒たちと聖母マリアが応答する。
ガリラヤ湖畔:マグダラのマリアの改心が描かれる。彼女の内面の葛藤と救済が音楽的に表現される。
カイザリア・フィリピとカペナウム:ペテロがキリストを「生ける神の子」と告白する場面。
終曲:「希望の囚人たちよ、要塞に帰れ」と歌われ、希望に満ちた雰囲気で第1部が締めくくられる。
第2部
序章:新たな動機が提示され、物語の緊張感が高まる。
裏切り:ユダの内面の葛藤と裏切りの動機が描かれる。彼の絶望と後悔が音楽に表現される。
ゴルゴタ:キリストの十字架上の死が描かれる。オーケストラが「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」を奏で、合唱が「まことにこの人は神の子であった」と応答する。
墓にて:復活の朝が描かれ、天使の合唱が「なぜ生ける方を死人の中に求めるのか」と歌う。
昇天:使徒たちが天使と共に賛美し、教会の設立への希望が示される。
音楽的特徴と動機の展開
エルガーは《使徒たち》でワーグナーのライトモティーフ技法を取り入れ、約80の動機を用いて作品全体を構築している 。主要な動機には以下のようなものがある:
「主の霊」:序章で提示され、作品全体を通じて神の導きを象徴する。
「キリストの祈り」:キリストの内面の苦悩と祈りを表現する旋律。
「教会」:教会の設立と信仰の広がりを象徴する動機。
「ユダの誘惑」:ユダの内面の葛藤と世俗的な欲望を表す旋律。
「昇天」:作品のクライマックスで用いられ、天への昇りを音楽的に描写する。
これらの動機は、登場人物の心理や物語の進行に応じて変奏され、作品に統一感と深みを与えている。
登場人物ごとの動機と他作品との関連
マグダラのマリア:彼女の動機は、罪からの解放と信仰への目覚めを象徴し、柔らかく感情豊かな旋律で表現される。
ユダ:彼の動機は、上昇する不協和音や下降する旋律で、内面の葛藤と絶望を描写する。
ペテロ:彼の動機は、《王国》でより明確に展開され、教会の礎としての役割を強調する。
これらの動機は、《ゲロンティアスの夢》や《王国》といった他の作品とも関連しており、エルガーの宗教的テーマの一貫性を示している。
演奏解釈上の注目点
合唱とオーケストラのバランス:エルガーは合唱とオーケストラを対等に扱っており、特に終曲ではその融合が求められる。
動機の明確な提示:各動機の提示と変奏を明確に演奏することで、物語の流れと登場人物の心理が伝わりやすくなる。
テンポとダイナミクスの変化:物語の展開に応じて、テンポや音量の変化を的確に表現することが重要である。
結論
《使徒たち》は、エルガーの宗教的三部作の中でも特に内面的な葛藤と信仰の旅路を描いた作品である。豊富な動機の使用と深い心理描写により、聴衆に強い感動を与える。演奏者にとっては、音楽的な技術だけでなく、物語への深い理解と表現力が求められる作品である。