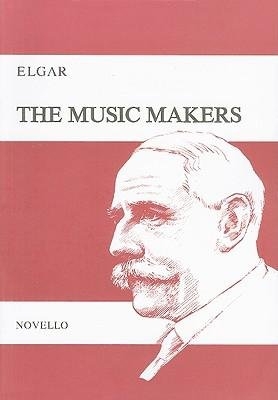『The Music Makers』における儀式性の構造
儀式の主題:芸術家としての自己奉納
この作品の核心は「We are the music makers, and we are the dreamers of dreams...」に代表される芸術家自身の自己定義である。ここでの儀式とは、詩人・作曲家=エルガー自身が「芸術を生み出す者たち」の代表として、その使命と苦悩、誇りと孤独をオーケストラと合唱を通じて演じるものとなる。
儀式の参加者(=役割の主)
詩人/語り手(合唱・メゾソプラノ):芸術家の魂の声そのもの。自らを孤高の存在として語り、社会からの疎外と同時に変革者としての自覚を語る。
エルガー自身(オーケストレーションと引用の設計者):彼は自己の過去作品を随所に引用することで、音楽的な“自伝”を構築する。自己を語る儀式において、過去の自作が回帰する様子は、まさに追悼と復活の儀式のように機能する。
聴衆(儀式の見届け人):この作品における儀式は、外的対象ではなく内的自己へ向かっており、聴衆はその通過儀礼を共感とともに目撃する存在となる。
引用された「エルガー自身」の音楽
『エニグマ変奏曲』『ゲロンティアスの夢』『海の絵』『愛の挨拶』などが引用され、まるで芸術家の一生を回想するような構造をとり、これは「自己の作品を通じて自己を奉納する」儀式的装置として機能する。
『The Music Makers』(1912年作曲)における自作引用は、この作品がエルガー自身による「音楽的人生回顧」あるいは「自己奉納の儀式」であるという視点を裏付ける重要な要素。以下に代表的な引用元と該当箇所を示す。
『The Music Makers』における引用作品一覧(代表的なもの)
交響曲第1番より
引用箇所:小節番号 120–123
該当テキスト:「We are the music makers」
内容:交響曲第1番のテーマが引用され、音楽を創造する者としての芸術家の役割が示されている 。英雄的な上昇音型。自己紹介のファンファーレ的意味合い。
『ゲロンティアスの夢』より
引用箇所:小節番号 50–53
該当テキスト:「We are the dreamers of dreams」
内容:この部分では、『ゲロンティアスの夢』のテーマが引用され、夢見る者としての芸術家の孤独と使命が表現されている 。
引用箇所:「dreams」という語が現れる箇所(具体的には第1部の中盤)
該当詩句:「And we are the dreamers of dreams」
解説:この引用は、芸術家の夢想家としての側面を強調し、霊的な旅路を象徴している。
『ゲロンティアスの夢』 第2部の一節
該当テキスト:「With wonderful deathless ditties…」
解説:魂の旅と永遠性を重ねるような流れ。
『威風堂々』第1番“Land of Hope and Glory” より
“We fashion an empire’s glory”/『威風堂々』第1番“Land of Hope and Glory” の旋律。/国民的栄光と芸術家の影の関係を皮肉的に描く。
『海の絵』"Sea Slumber Song"より
引用箇所:小節番号 84–87
該当テキスト:「Wandering by lone sea-breakers」
内容:『海の絵』の冒頭が引用され、孤独な海辺をさまよう芸術家の姿が描かれている 。自然と孤独の詩句にふさわしく、静謐な海のイメージを重ねる。《海の絵》の主題を引用することで、孤独な海辺をさまよう芸術家の姿を描写している。
『エニグマ変奏曲』より「ニムロッド」
引用箇所:小節番号 234–237
該当テキスト:「We fashion an empire's glory」
内容:『エニグマ変奏曲』の「ニムロッド」が引用され、芸術家が帝国の栄光を形作る存在であることが強調されている 。
該当テキスト:「We in the ages lying…」
芸術の永続性、友情、深い精神性を象徴する。エルガーの最も崇高な主題のひとつ。
引用箇所:小節番号463–470(第5節)
該当詩句:「But on one man's soul it hath broken / A light that doth not depart」
解説:エルガーの親友であるA.J.イェーガーへの追悼として、《ニムロッド》の主題が引用されている。
《エニグマ変奏曲》の主題
引用箇所:冒頭のオーケストラ導入部(小節番号はスコアによって異なるが、作品冒頭)
該当詩句:「We are the music makers」
解説:エルガーは、《エニグマ変奏曲》の主題を用いて、芸術家の孤独と使命感を象徴しており、この主題は作品全体を通じて繰り返され、芸術家の存在意義を強調している。
《ヴァイオリン協奏曲》からの引用
引用箇所:小節番号657–661
該当詩句:「A little apart from ye」
解説:《ヴァイオリン協奏曲》の主題を引用することで、芸術家の孤高と内省的な側面を強調している。
終盤の穏やかな再現部/『愛の挨拶』/私的な愛と普遍的芸術の交差。音楽家としての原点回帰。
引用箇所:小節番号 160–163
該当テキスト:「And we are the dreamers of dreams」
内容:ヴァイオリン協奏曲の旋律が引用され、夢見る者としての芸術家の内面が表現されている 。
《交響曲第2番》の終楽章からの引用
引用箇所:小節番号483–487
該当詩句:「And his look, or a word he hath spoken / Wrought flame in another man's heart」
解説:《交響曲第2番》の終楽章の主題を引用することで、芸術家の影響力と感情の伝播を表現している。
《ルール・ブリタニア》と《ラ・マルセイエーズ》の引用
引用箇所:「Out of a fabulous story / We fashion an empire's glory」という詩句に対応する部分
解説:これらの国歌の引用は、音楽が国家や帝国の栄光を形作る力を持つことを象徴している。
補足:なぜ引用されるのか?
これらの引用は単なる懐古ではなく、芸術家が自己の業績を再召喚し、それをひとつの象徴として祭壇に置くという、まさに儀式的な行為。詩人(=芸術家)が言葉を紡ぐと同時に、音楽家(=エルガー)はそれに応えるように過去作を編み込み、まるで「自己自身で作った祭壇の上で、自己を讃えるレクイエム」を奏しているかのようである。
エルガーは『The Music Makers』において、これらの自己引用を通じて、芸術家としての自己認識や孤独、社会との関係性を音楽的に表現している。特に、『エニグマ変奏曲』の「ニムロッド」の引用は、芸術家の孤独と崇高な使命感を象徴しており、エルガー自身がこのテーマを「芸術家の孤独を表現している」と述べている 。
構成と展開の儀式的意味
冒頭の静謐な導入 → 内省の始まり
中間部の激しさ → 苦悶と孤独
終結部の穏やかさ → 超越と自己受容
アングル作者:エルガー自身
この作品では、他者の魂を扱った『ゲロンティアスの夢』や、他者の作品を補筆した交響曲第3番と異なり、完全に「自己の儀式」であるという点が特異。エルガーは詩人の声を借りながら、自身を「音楽を作る者」として祭壇に捧げているといえるだろう。
このように、『The Music Makers』は自己を奉納する芸術家の通過儀礼という意味において、深く儀式的な構造を持っていることがわかる。
このように、引用される作品はすべて「エルガーの芸術的人生における節目」を象徴している。特に『威風堂々』や『Nimrod』は世俗的成功と精神的信仰の両極を象徴しており、これが『The Music Makers』の深い二面性(誇りと孤独)と結びついている。