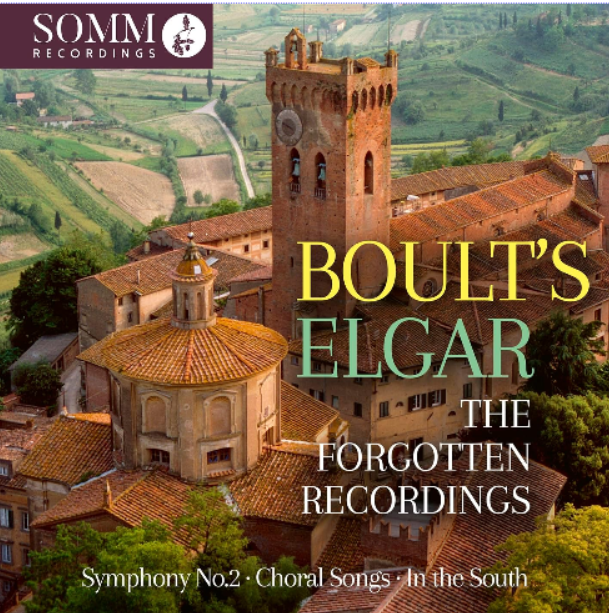失われたLPからの復活 ― サー・エイドリアン・ボールト1963年の遺産
SOMM Recordingsとラニ・スパーの協力により、エドワード・エルガーの音楽を生涯にわたり擁護したサー・エイドリアン・ボールトの功績を浮き彫りにする、長く忘れ去られ顧みられなかった録音がリリースとなった。
1918年2月17日、戦時下のロンドンで、28歳のエイドリアン・ボールトはエドワード・エルガーの自宅を訪れ、翌晩クイーンズ・ホールで初指揮する予定だった『南国にて』の演奏詳細について協議した。1944年、再び戦火のさなか、ボールトはBBC管弦楽団との放送演奏でこの序曲を再び指揮することとなる。
エルガーは1911年5月24日、クイーンズ・ホールで自身の交響曲第2番の初演を指揮したが、彼自身の認める通り、またボールトの記述によれば「実にかなり失敗作」であった。第一交響曲の成功に影を潜め、第二交響曲は控えめな礼儀正しさをもって迎えられた。
1920年3月16日、ボールトがロンドン交響楽団を指揮してこの交響曲を初演した後、エルガーは彼に手紙を書いた。「交響曲の素晴らしい指揮に感謝の言葉を贈ります。この作品を慈しむように扱ってくださったことに深く感謝し、私の将来の評判はあなたの手に委ねられていると感じています」
そしてその言葉は現実となった。ボールトはこの交響曲を70回以上も演奏し、彼の熱心な擁護によって聴衆がこの作品に徐々に親しむようになったのである。
今回SOMMレーベルから初CD化される第2交響曲の録音は、1963年9月、サー・エイドリアンが75歳の誕生日を迎える数ヶ月前にスコットランド国立管弦楽団によって行われた。ナイジェル・シメオネ(『エドワード・エルガーとエイドリアン・ボールト』著者)は本録音について「テンポ選択における揺るぎない『正しさ』の感覚、各楽章の広範な構造に対する驚異的な把握力、そして揺るぎない誠実さと確信に満ちた演奏」と評している。ボールトの指揮者としての初期経験の一部は、オックスフォード大学在学中の合唱団指導にあった。本リリース第2ディスクには、1907年から1914年にエルガーが作曲した10曲の無伴奏合唱曲(ボールト指揮BBC合唱団)を収録した1967年7月のBBCラジオ放送音源を収録。この2枚組CDには、BBCによるボールトの洞察に満ちたインタビュー3本も収録されている。これには、サー・エイドリアンがエルガーの娘キャリスと『エニグマ変奏曲』について語り合う様子や、エルガーとの協働による『交響曲第2番』と『南国にて』についての彼の認識も含まれている。
1963年9月、サー・エイドリアン・ボールトがグラスゴーで録音したエルガー交響曲第2番は、長らく「失われた録音」として知られてきた。短命に終わったウェーバリー・レーベルのために収録され、当時はごく限られた形でしか流通せず、後年EMIにテープが渡ったにもかかわらず、ボールトの公式全集からも漏れてしまった。そのため、半世紀以上の間「幻のボールト盤」としてエルガー愛好家に語り継がれる存在であった。
演奏そのものは、ボールトの最盛期を過ぎた時期にあたるが、なお彼の指揮が持つ厳格な造形力と音楽の流れを決して失っていない。第1楽章では速すぎず遅すぎず、あくまでも「音楽そのものが自然に語る」テンポ運びを徹底し、他の録音に見られるようなやや乾いた響きよりも、柔らかさと暖かみが強調されている。特に第2楽章の葬送行進曲では、響きの渋さと深い内省が際立ち、ボールトの中でも最も抑制的でありながら魂のこもった表現が聴かれる。
第3楽章の柔和な流れは、後年のEMI録音よりも一層透明感があり、ボールトが「単なる懐古ではなく、純粋な音楽美」としてエルガーを提示している点が印象的である。そして終楽章では、劇的な高揚よりも音楽の大きな呼吸と精神的広がりに重きを置いており、聴き手に深い静けさと余韻を残す。
この録音の最大の価値は、「ボールトがエルガー第2をどのように成熟の時期に扱っていたか」を知ることができる点である。初期の録音に見られる若々しい推進力とも、晩年の録音に見られる枯淡の境地とも異なる、いわば「中期ボールト」の視点からのエルガー像である。音質は当然ながらスタジオ録音として十分に鑑賞に堪え、歴史的記録以上の音楽的充実を備えている。
エルガー演奏史の資料的価値はきわめて大きく、単なる「発掘盤」ではなく、正規ディスコグラフィーに位置づけられるべき重要な録音である。