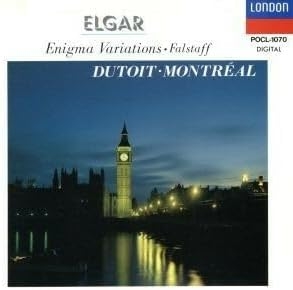デュトワのエニグマ
日時:2000年12月16日
会場:NHKホール(東京)
指揮:シャルル・デュトワ
ヴァイオリン:レオニダス・カヴァスコ
管弦楽:NHK交響楽団
曲目 ヒンデミット/交響曲「画家マティス」
チャイコフスキー/ヴァイオリン協奏曲
エルガー/エニグマ変奏曲
2000年12月16日、NHKホールにおいてシャルル・デュトワがNHK交響楽団を指揮して披露したエルガー《エニグマ変奏曲》は、同氏がモントリオール交響楽団と録音した既存音源と多くの点で類似したアプローチを採用していた。すなわち、細部にわたり練られた管弦楽の色彩と音響構造の明晰さを前面に出した演奏であり、エルガー解釈におけるフランス=スイス系指揮者の特性がよく現れた一例といえる。
とりわけ「ニムロド」変奏におけるダイナミクスの制御は注目に値する。デュトワは多くの演奏家が感情過多により早急なクレッシェンドを行い、クライマックス手前で表現の頂点に達してしまうという「構造の先走り」を回避し、冷静にクレッシェンドを段階的に制御した。これはエルガー自身の録音やアドリアン・ボールトら初期の英国系指揮者が示した伝統的な解釈とも呼応する手法であり、楽曲の弧を崩さぬバランス感覚が感じられる。
また、変奏「トロイト」(Troyte)におけるティンパニの一撃の強調は、モントリオール響との録音時と同様に実演でも再現され、デュトワの《エニグマ》演奏における「署名」ともいうべき個性的な処理として注目される。これはエルガーのユーモアやリズム的意外性を強調する意図と解釈され、デュトワのエルガー観におけるフランス的軽妙さと構成感の融合を象徴している。
他方、NHK交響楽団の演奏は必ずしもデュトワの意図に完全に追随したとは言い難く、特に細部のニュアンスや即興的反応において、モントリオール交響楽団との録音で達成された高次の合一感には届いていない印象を与えた。すなわち、指揮者のコンセプトが明確であったにもかかわらず、実演における全体の緊密度には若干の開きがあったことは否めない。
とはいえ、2000年代初頭における日本国内での《エニグマ変奏曲》実演の水準としては特筆すべき成果であり、特にデュトワの楽曲構造把握とダイナミクス制御において極めて高い完成度を示したことは、エルガー解釈史の中で改めて記録されるべきである。
全体的に満足のゆく演奏であるが、オケがN響でなくモントリオール交響楽団だったら・・・というのは贅沢な望みなのであろう。