エルガー未完のオラトリオ《最後の審判》──宗教三部作の果てに
エドワード・エルガー(1857–1934)が晩年に構想していた大規模オラトリオ《最後の審判(The Last Judgement)》は、《ゲロンティアスの夢(1900)》《使徒たち(1903)》《神の国(1906)》という宗教三部作(いわゆるエルガーの"SpiritualTrilogy")の最終作、あるいは第四作として、彼自身の終末的な世界観と宗教的構想を結晶させる試みであった。しかしこの作品は、スケッチと断片的な草稿を残したのみで、彼の死によって未完に終わった。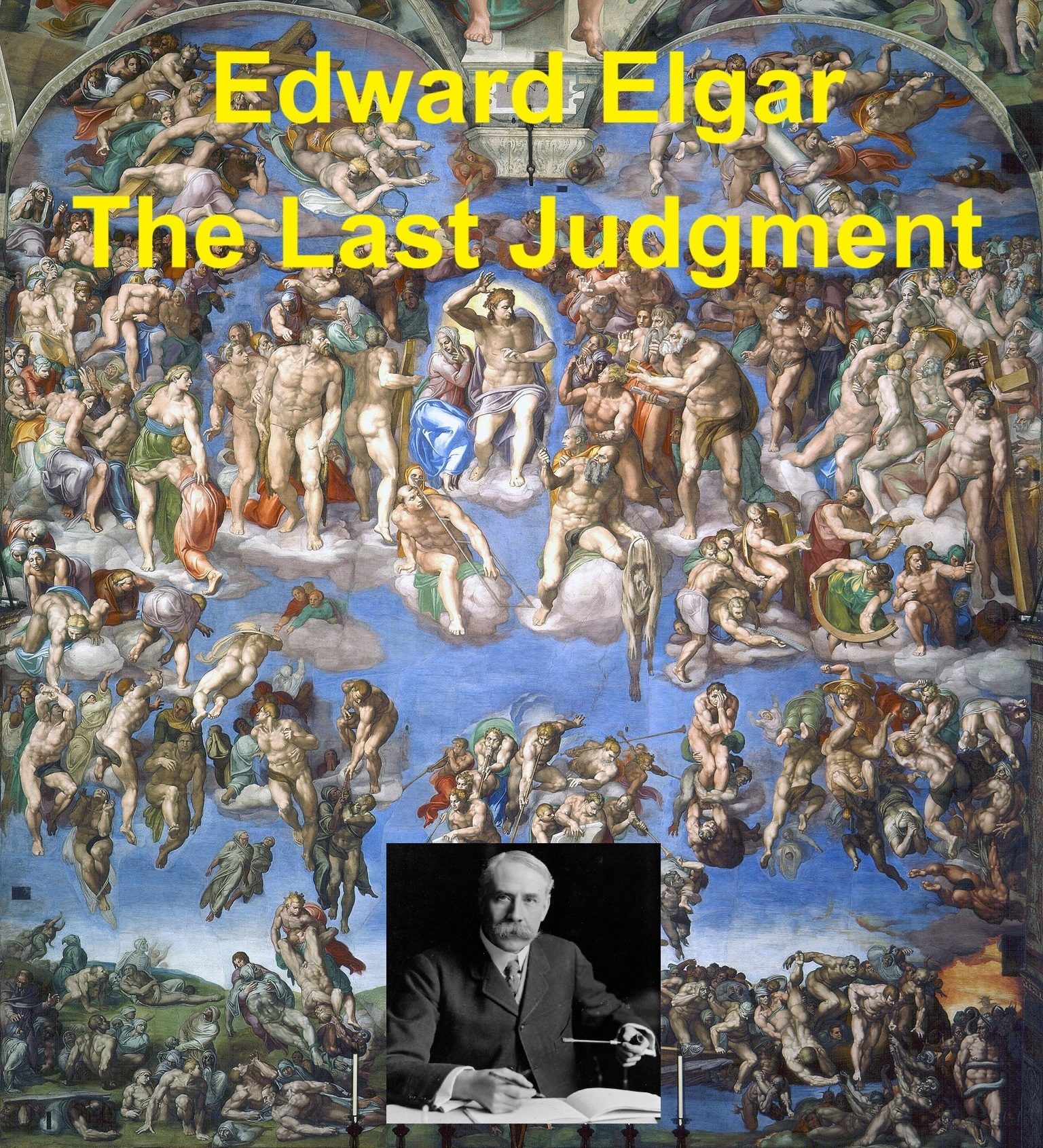
宗教オラトリオ三部作との連続性と展望
《最後の審判》は、その主題からして《ゲロンティアス》の死後の魂の旅、《使徒たち》における福音伝道の始まり、《神の国》での教会共同体の誕生を経たうえで、救済史の完結点=終末の日を描くものとなるはずであった。これらの作品を通じて、エルガーはしばしば「個」の視点(ゲロンティアス)と「共同体」の視点(使徒たち、教会)を往還させてきたが、《最後の審判》においては、全人類が審かれる終局的瞬間という普遍的テーマが正面から扱われる予定だった。
この計画は1900年代後半から漠然と意識されていたとされ、1912年にはロンドンで開かれた宗教音楽祭(Three Choirs Festival)のプロデューサーに宛てた手紙において、エルガー自身が「Judgement or Apocalypseのようなテーマに取り組む可能性がある」とほのめかしている。
2010年に発見された自筆スケッチ
この未完作品の存在は以前から知られていたが、2010年、英国王立音楽大学 (RCM)に保管されていた資料の中から、**《最後の審判》のために書かれたと見られる10ページ以上の自筆草稿(スケッチ)**が発見された。これには、いくつかの旋律断片、オーケストレーションのアイデア、さらにはテキストの一部(『ヨハネの黙示録』の抜粋と見られる箇所)などが含まれており、エルガーが《神の国》以降も宗教オラトリオの構想を断続的に温めていたことが裏付けられた。
この草稿の中には、《神の国》第3部で現れる「神の都」モチーフに類似する素材や、《ゲロンティアスの夢》で使われた和声語法との関連も見られ、彼の「儀式性」の音楽的語彙がここでも展開される可能性があったことを示している。
さらに注目すべきは、これらのスケッチにショーファー(ユダヤ教の儀式用角笛)を模したファンファーレ的モチーフが含まれていた可能性である。エルガーは《使徒たち》の冒頭においてすでに「ショーファー風」モチーフを使用しており、《最後の審判》でも終末を告げる「角笛」の音としてこのモチーフが回帰することは、音楽的・象徴的に極めて自然な展開であっただろう。
「儀式性」の極点としての《最後の審判》
エルガーの宗教オラトリオ群に共通する特徴として、「典礼構造」「ファンファーレ」「反復句」などに支えられた**儀式性(rituality)**がある。《最後の審判》はその最終到達点として、審判の書が開かれ、死者が呼び出され、角笛が鳴り響くという壮麗な典礼劇を志向していたと推測される。
また、彼の音楽にしばしば登場する「12」という数(12使徒、12の調、12人の声部など)も、本作においては**「イスラエルの12部族」や「新エルサレムの12の門」**という黙示録的象徴と重ね合わされ、象徴的・構造的なモチーフとして扱われていた可能性がある。
現代の補筆への可能性と課題
エルガー未完の交響曲第3番を補筆したアンソニー・ペイン(Anthony Payne)は、この《最後の審判》のスケッチにも一定の関心を寄せていたが、同作の補筆には着手していない。残された素材の断片性のため、交響曲第3番のような補筆完成は現実的ではないという見方が強い。
とはいえ、2010年の草稿発見以降、学術的・創作的関心は高まっており、21世紀的視座からの「補筆的再構築」やメタ・オラトリオ的上演(他の3作品からの素材を引用しつつ構成するような方法)といった、新たな試みへの道も開かれつつある。
結語
エルガーの《最後の審判》は、宗教三部作の完結を夢見ながら果たせなかった、彼の宗教的・芸術的遺産の「黙示録」である。残された草稿はわずかであるが、その背後には、神秘と典礼が渾然一体となった壮大な音楽的ヴィジョンが脈打っている。たとえ音として鳴り響くことが叶わなくとも、この未完の遺作は、彼のオラトリオ世界の最終的な天蓋として、今なお我々の想像力を刺激し続けている。
《最後の審判》(The Last Judgement)は、彼の壮大な三部作構想の最終章として構想され、完成には至らなかったが、2010年に発見された自筆譜の断片は、この作品の構想と音楽的内容を探る手がかりを提供している。
概要と背景
エルガーは《使徒たち》(1903)と《神の国》(1906)に続く三部作の完結編として《最後の審判》を構想していた。
2010年発見の自筆譜とその意義
2010年に発見された自筆譜の断片は、エルガーが《最後の審判》の構想を具体化しようとしていた証拠である。
音楽的分析と動機構造
自筆譜の断片からは、エルガーが《最後の審判》において新たな音楽的要素を模索していたことがうかがえる。
補筆された場合の構成案
もし《最後の審判》が補筆されるとすれば、以下のような構成が考えられる:
序奏:黙示録の序章
オーケストラによる荘厳な序奏。
第1部:審判の兆し
ソリストと合唱による緊張感のある展開。
第2部:最後の審判
合唱とオーケストラによる壮大なクライマックス。
第3部:新しい天と地
穏やかで希望に満ちた終結。
他作品との関連性
《最後の審判》は、エルガーの他のオラトリオ作品と密接に関連している。
《使徒たち》との関連:
《神の国》との関連:
結論
エルガーの《最後の審判》は、彼の宗教的オラトリオ三部作の完結編として構想されたが、完成には至らなかった。2010年に発見された自筆譜の断片は、この未完の作品の構想と音楽的内容を探る貴重な手がかりである。今後、これらの資料をもとにAIを駆使するなどして補筆や演奏が試みられることで、エルガーの壮大な構想が現代に蘇る可能性がある。



