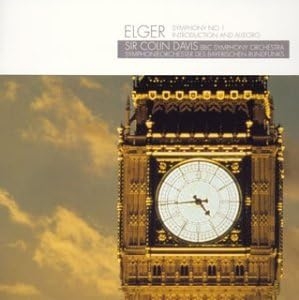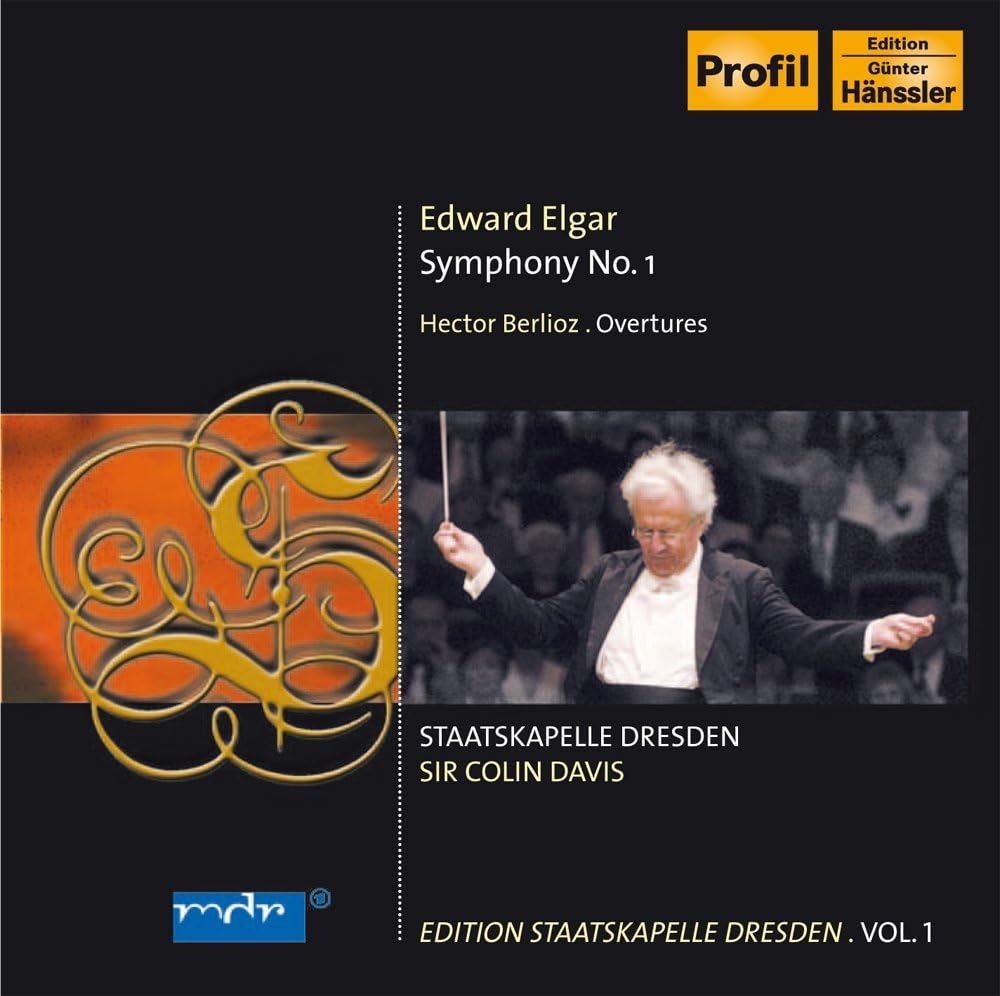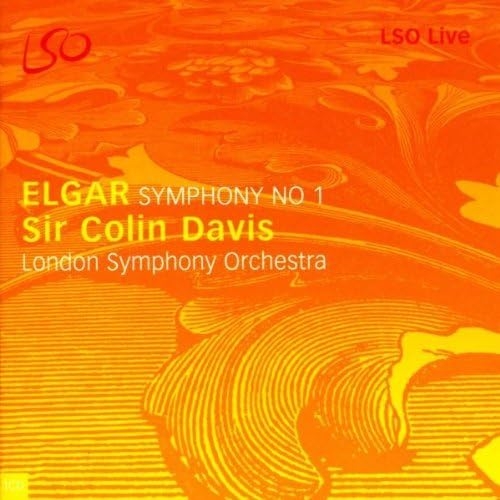コリン・デイヴィスのエルガー1番
ロンドン響との来日公演においてエルガーの交響曲第1番の素晴らしい名演を繰り広げたサー・コリン・デイヴィス。
実演で接した同曲としては3本の指に入る名演奏だったと記憶している。
その日本公演の直前にLSOシリーズとしてエルガーの交響曲の録音を行い、こちらもまた端正な仕上がりにノーブルの極みの名録音となっているのは周知の事実だ。
彼の指揮によるこの曲は実に3種類に及ぶ。
最初に1985年にBBC響との演奏によるRCA盤である。
2度目が1998年にドレスデン・シュターツカペレを指揮したライブ盤。
3度目が2001年のロンドン響とのエルガーチクルスの一環として行われたLSO盤。
どれも素晴らしいのであるが、3種類あるサー・コリンのエルガー1番が、全部全く違うテイストであるということが大きな特徴としていえるのである。
どの指揮者でも年齢とともに解釈が変わっていくものであるが、ことサー・コリンに関しては「本当に同一人物か?」と思いたくなるほどのドラスティックな変化を見せてくれる。
85年のRCA盤は、なんというかまだ完全に出来上がっていないぎこちなさを感じないではない・・・といっても、これは後の新しい盤と比較したら、ということになる。演奏自体は文句のつけようのないビシっと締まったものである。しかし、これがコリン・デイヴィスの解釈の最終形ではないことは後の盤を聴くことによって明らかにされる。
さて、問題なのが98年のドレスデン・ライブである。これはまた凄まじい熱気・・・いや、狂気といってもいいかもしれない。
我々の知っているサー・コリンではない。こんなに荒れ狂う嵐のようなエルガーは聴いたことがない。
ティンパニの狂騒、ブラスの咆哮、ストリングスのカンタービレ。どれも凄まじい。
まるで1940年代のベルリンフィルを振っていたころのフルトヴェングラーみたいだ。
ここで、少し思い当たる演奏がある。
それがカール・シューリヒトが1963年にバイエルン放送響を指揮したブルックナーの交響曲第9番のライブ録音だ。
シューリヒトのブル9といえば、ウィーンフィルとのスタジオ録音が名演として知られている。
まるで水墨画を思わせる端正で美しい表現はシューリヒトの代名詞とさえなっている録音だ。
しかし、バイエルンでのライブは全く違う。まるでショスタコーヴィッチのシンフォニーのように凄まじい嵐!。
いったいシューリヒトどうしちゃったの?と心配になるくらい解釈が違う。
コリン・デイヴィスのドレスデン盤はこれと全く同じ。
ドレスデン、バイエルンといったドイツのオケにかかると、かくも様相が違ってしまうのか・・・・。
とはいえ、シューリヒトとバイエルンのブル9とデイヴィスとドレスデンのエル1どちらも好きで愛聴盤なのであるが・・・。
3度目のLSO盤。これは彼の最終到達点なのだろう。東京でのライブ演奏もほぼ同じ解釈で同じ輪郭を描いていた。
そこには正に王道の貫禄さえ感じられた。
最終地点にたどり着いた安心感と安定感がこの上なく心地よい演奏となっている。
ドレスデンでのラフな面は除去されており、いかにも英国音楽とはこういうものだ!とでも言いたげな雄弁さを内包しつつ盛り上げるところはしっかり締める。
ドレスデンの時のラフさの名残といえば、第2楽章スケルツォでの打楽器群の大音量だろう。打楽器と金管楽器の間にアクリル板が設置されて、金管楽器奏者の鼓膜が破れるの防ぐためのものだろう。気が付いた人も多いと思う。それほど凄い大音量なのだ。CDで聴いてもちゃんとわかるくらいである。
というわけで、コリン・デイヴィスの3種類のエル1。どれも違うテイスト。これほど楽しめる指揮者はいないと思う。