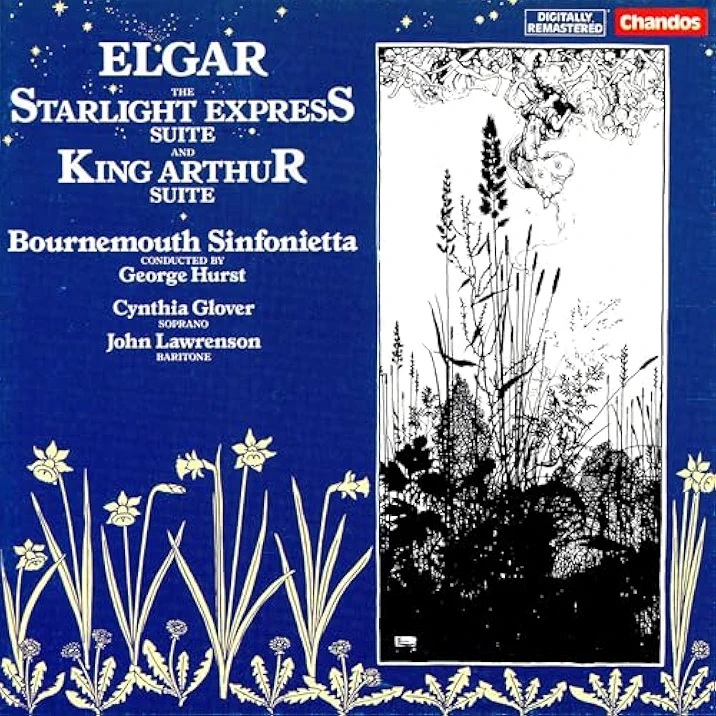劇付随音楽《アーサー王》(Arthur, Op. 56)
エルガーの劇付随音楽《アーサー王》(Arthur, Op. 56)は、1923年に作曲された作品で、劇作家ローレンス・ビニョン(Laurence Binyon)による戯曲『アーサー』の上演のために書かれた。エルガーはこの劇のために全体で27の音楽ナンバー(前奏曲、幕間音楽、シーンの転換など)を作曲し、その総演奏時間はおよそ50分に及ぶ。
概要
『アーサー』は中世ブリテンの伝説的王、アーサー王とその円卓の騎士たちの物語を描くものであり、ビニョンの脚本はシェイクスピア劇のような五幕構成である。
エルガーの音楽はこの劇のさまざまな場面――戦争、恋愛、裏切り、死――を情感豊かに彩りながら、古代ブリテンの神話的世界を壮大に描き出す。
エルガー自身は、劇音楽のような“応用音楽”を通常の作品よりも軽く見る傾向があったが、この《アーサー王》には彼の創作の中でも特に情熱的なモチーフが現れており、彼の交響作品や宗教的オラトリオに通じる要素が含まれている。
音楽的特徴
本作において特筆すべき点は、以下のようなエルガー特有の作曲技法と主題的構造である。
動機的統一性:物語全体を貫くモチーフ(アーサーの主題、モルドレッドの不穏な動機、ランスロットとグィネヴィアの甘美な旋律など)が、劇の場面に応じて変奏・変形されて再登場する。
宗教性と儀式性:《ゲロンティアスの夢》《The Apostles》に通じるような、荘厳な合唱風書法や、象徴的なファンファーレが使われる。
中世的世界観の音楽化:ダンス風の場面音楽やホルンによる騎士的な主題により、中世の騎士道世界を音楽で再現している。
主な楽曲
前奏曲
:重厚な和声と幻想的な雰囲気を持つオープニング。物語の壮大なスケールを予感させる。
アーサーのモチーフ
:堂々たる金管主題で表され、英雄としての威厳と悲劇性を同時に帯びている。
愛の場面(グィネヴィアとランスロット)
:甘美な旋律線が印象的で、エルガーらしいロマンティシズムが光る。
戦いと裏切りの場面
:不協和音や強烈なリズムにより、モルドレッドの陰謀と戦争の緊張感を描写。
終幕の哀歌
:アーサー王の死と、それに続くブリテンの滅びを象徴的に描いた静謐で崇高な音楽。
現代における評価と復活
この劇音楽は1923年の上演後、長らく忘れられていたが、21世紀になってから再評価が進み、近年ではCD録音や演奏会形式での上演も行われている。特にエルガー研究者の間では、この作品はチェロ協奏曲以降での大作となっている点が注目されている。
とりわけアーサーのモチーフは、**エルガー晩年の未完交響曲(交響曲第3番)**の素材にも再使用されている。アンソニー・ペインによる補筆版ではその回想的役割が明確に示されている。
結語
エルガーの《アーサー王》は、劇音楽というジャンルにとどまらず、彼の作曲活動の重要な一章をなす作品である。騎士道、愛、裏切り、そして崇高な死という壮大な主題を、緻密で象徴的な音楽で描き出したこの作品は、今後さらに注目されるべきエルガーの“秘められた傑作”と言えるだろう。
エルガーと騎士道――《アーサー王》にみる中世的理想の音楽化
エルガーの音楽には、しばしば**「高貴なる精神性」への憧れが通奏低音のように流れている。その根底にあるのが、19世紀末から20世紀初頭にかけて英国社会を覆っていた「騎士道的理想」への共鳴である。エルガーは敬虔なカトリック信仰者であると同時に、ヴィクトリア朝英国における道徳的・象徴的秩序にも強く共感していた作曲家であり、その作風には騎士道物語に通じる崇高さ、忠誠、そして悲劇性**が色濃く刻まれている。
その結晶とも言える作品が、劇付随音楽《アーサー王》(Arthur, Op. 56)である。1923年、劇作家ローレンス・ビニョンの戯曲『アーサー』のために書かれたこの音楽は、エルガーの創作の中でも特異な位置を占めている。本作は単なる劇伴にとどまらず、アーサー王とその騎士たちの物語を通じて、理想主義と人間の弱さのせめぎ合いを描き出す精神的ドラマとして構成されている。
アーサー王は、忠義・栄光・信仰といった中世的価値観の象徴であり、エルガー自身が好んで語っていた「騎士道の魂」の化身である。彼がこの題材に特別な情熱を注いだ背景には、自らの芸術観――音楽を通じて内面的な高貴さや倫理観を語るべきだという信念――が関係している。
エルガーは本作において、いくつかのモチーフ(アーサーのファンファーレ、モルドレッドの陰謀主題、グィネヴィアとランスロットの愛の旋律など)を用いて物語の構造を音楽的に支えると同時に、作品全体に一種の「儀式性」を与えている。とりわけアーサー王の主題は、英雄性と孤独、理想と滅びの予感を併せ持つ旋律として描かれており、エルガーの交響曲的思考ともつながる重要な素材である。
事実、彼の死後にアンソニー・ペインによって補筆された《交響曲第3番》には、《アーサー王》からの素材が明確に引用されており、アーサー王のモチーフが「再臨」するような構造が認められる。これは単なる引用ではなく、エルガーにとってアーサー王という存在が一種の理念であったことの象徴である。
また、《アーサー王》の音楽には、《ゲロンティアスの夢》やオラトリオ三部作に通じる宗教的荘厳さも備わっており、騎士道と信仰が音楽的に融合した構造となっている点も見逃せない。すなわち、エルガーにおける騎士道とは、単なる歴史的主題ではなく、人間存在の倫理的中核を象徴する理念として扱われているのである。
結語
エルガーにとって「騎士道」とは、過去への憧憬や物語的装飾にとどまらず、音楽を通じて表現されるべき崇高な人間性と精神の在り方そのものであった。《アーサー王》はその理想をもっとも明確な形で体現した作品であり、彼の芸術の核心にある「高貴なるもの」への讃歌と言える。
エルガー他の作品における中世的英雄譚や騎士道的美学
◆《黒騎士》The Black Knight, Op. 25(1892)
典型的なロマン派騎士譚であり、エルガーの初期カンタータ作品として最も騎士道的な世界観を備える。ルートヴィヒ・ウーラントのバラード詩に基づくこの作品は、謎めいた黒騎士が宮廷に現れ、忠義・名誉・戦争と死をめぐるドラマを展開する。音楽的にはリスト風の交響的詩的様式と、後のエルガーのオラトリオ的語り口との折衷が見られ、**中世的モチーフ(角笛、行進、戦闘、神秘)**が豊かに織り込まれている。
この作品では、騎士道の光と影──華麗な理想と破滅の運命──が対比的に描かれており、後の《ファルスタッフ》や《アーサー》への序章とも捉えうる。
◆《オラフ王》King Olaf, Op. 30(1896)
ロングフェローの詩に基づくこの作品は、ノルウェーの王オラフによる異教世界との戦いと改宗、殉教に至る道のりを描くカンタータである。ここに描かれるのは、まさに**信仰と剣を携えて闘う中世の「聖なる騎士」**の姿であり、キリスト教的騎士道の理想が色濃く反映されている。
オラフは「王であり戦士であり聖人」という三重の属性を持ち、音楽はその内面的葛藤と勝利を、荘厳かつ劇的に描いている。騎士道=聖戦的倫理という側面において、エルガー作品の中で最もストレートな表現といえる。
◆《カラクタクス》Caractacus, Op. 35(1898)
こちらは中世ではなく古代ブリテンの物語だが、抵抗の英雄としての王カラクタクスが描かれ、祖国愛・勇気・高潔な自己犠牲といった、騎士道的理想の萌芽を見ることができる。
カラクタクスはローマに対して反旗を翻し、敗北してもなお誇り高く振る舞う。最終的には敵である皇帝クラウディウスの前で毅然とした態度を示し、赦される。この姿勢は、騎士道における「高貴なる敗北(noble defeat)」の典型であり、音楽もそれに呼応して、勇壮な行進曲、神秘的な祈り、英雄的終曲をもって展開される。
◆比較と総括
《黒騎士》→《オラフ王》→《カラクタクス》→《アーサー》という流れで見たとき、エルガーは一貫して「騎士道=個人の高貴なる理想と行動規範」として捉え、それを中世ロマン、宗教的英雄譚、民族的抵抗譚、そして神話的王物語へと昇華させていったといえる。
したがって、「エルガーと騎士道」を主題にする場合、これら3作品(+《アーサー》)を中核に据え、他の作品(《ファルスタッフ》《ゲロンティアス》《使徒たち》など)を精神的・象徴的延長線上に位置づけるのが最も有効な構成となるであろう。