エルガーサウンドとは何か?
エドワード・エルガーは1932年に自作ヴァイオリン協奏曲の録音を行った。
この時、ソリストに迎えられたのは当時16歳のユーディ・メニューイン少年。
そのメニューインの演奏を審査(?)するために彼らは顔を合わせた。

メニューインは老作曲家の前でヴァイオリン協奏曲のソロの出だしを緊張しながら弾いてみせる。
そこでエルガーはこう言ったという。
「うん、何も問題ない。それで行こう」
とだけ言うと楽しみにしてた競馬観戦へと出かけてしまったという。
実際に出来上がった録音は素晴らしく、未だにこれを超える名演はほとんど誕生していない。
そのメニューインとの録音に先立ってエルガーは、彼のヴァイオリンの弟子でもあるマリー・ホールのソロで、ハイライト版ながらヴァイオリン協奏曲の録音を行っている。
これもまた素晴らしい演奏である。

ホールとメニューインの音色に共通するもの。
それは一言でいうと温かい音色。
倍音が豊かに伸び、そして横に広がるような包容力をもった音色。
16歳のメニューインは、技術的にはすでに完成されていたが、何よりも「純粋な魂の声」をそのまま音にしていた。エルガーが「問題ない」と言い残して競馬へ出かけた逸話は、単なる気まぐれではなく、若き奏者の中に、作品に込めたものがすでに内在していると確信したがゆえの言葉であろう。
不思議なことに、エルガーの名演奏を繰り広げる演奏家にこういう音色を持つ人が多い。
例えば、ジャクリーヌ・デュ・プレ、そしてジョン・バルビローリやエイドリアン・ボールト。
そして、メニューインや彼の弟子であるリランド・チェンなど。
ジャクリーヌ・デュ・プレが奏でた《チェロ協奏曲》における音色には、それが如実に表れている。第1楽章冒頭の低音弦による語りは、単なる主題の提示を超え、まるで遠く過ぎ去った日々を追憶するかのような深い感情を帯びている。デュ・プレのチェロの音色は、明瞭にして曖昧、個人的にして普遍的という矛盾した要素を同時に含み、まさにエルガーが求めた「詩的語り」の体現者と言えよう。
ジョン・バルビローリの解釈はその最右翼に挙げられる。彼の《交響曲第1番》における演奏は、テンポを急がず、細部をじっくりと彫琢しつつも、全体として大きなうねりを持ち、エルガー作品に通底する「ノスタルジアと希望」が有機的に絡み合う。彼の棒からは、一切の冷たさが排され、代わりに終始温かな人間的呼吸が作品全体を貫いている。
この包み込むような抱擁力と温かい音色。
これがエルガーをして「問題ない」と言わしめたものではないだろうか?
エルガーの曲というのは、如何に優れたテクニックでも描き切れない「心」の部分がある。
作曲家と演奏家の、心のある資質が同化した瞬間に、エルガー作品の名演奏が生まれるのだと思う。
逆の例を挙げればヤッシャ・ハイフェッツが演奏したものがある。
確かにヴィルトオーゾで鳴らしたハイフェッツにかかると、この難曲が全く難曲に聞こえないくらいの切れ味を見せる。
そのシャープさはまるで刃物のようだ。
確かに凄い演奏だとは思う。
しかし、エルガーの心の部分とは随分遠いところに位置するものだ。
感心はするが感動には程遠い。
彼のエルガー演奏は、完璧な技巧と明晰な構成力を誇ってはいるが、「心の同化」において何かが欠けている。ハイフェッツの音は研ぎ澄まされた刃物のようであり、エルガー作品に必要な「ぬくもり」や「ためらい」「人間的揺らぎ」が感じられない。もちろん演奏としては非の打ち所がないが、あくまで「観賞の対象」であって、「共感の対象」とはなり得ない。
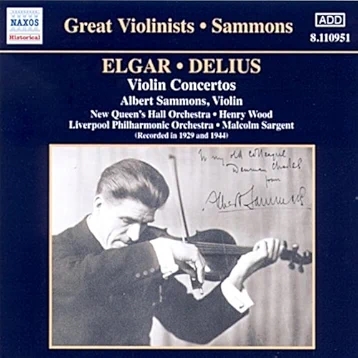
エルガー・サウンドとは何か。それは単に音響的なスタイルや記号ではなく、作品に内在する精神的温度と、演奏家の内面とが一致したときに生まれる、極めて個人的かつ共感的な響きである。
この「エルガー・サウンド」は、幾つかの音楽的・演奏的要素によって特徴づけられるが、最も本質的なのは「音色の抱擁力」とでも言うべきものであろう。すなわち、音そのものが語りかけ、包み込み、慰め、時には内奥の痛みに寄り添うような響きである。
エルガー・サウンドとは、単に「英国的」といった言葉では括りきれない、作曲者自身が生きた人生、内面、理想、失意、そしてそれらを超えてなお残る希望の総体を、音楽として再現することである。それは、演奏家が自らの心を音に込めることなしには実現されない。
音色の質感、フレーズの歌わせ方、テンポの「迷い」、和声のニュアンスの積み重ね──そのすべてが、ひとつの方向へと収斂するとき、そこに「エルガー・サウンド」が立ち現れるのである。それは一過性の音楽現象ではなく、演奏家と聴き手の双方の魂に、静かに、しかし深く沈降していく共鳴の響きである。



