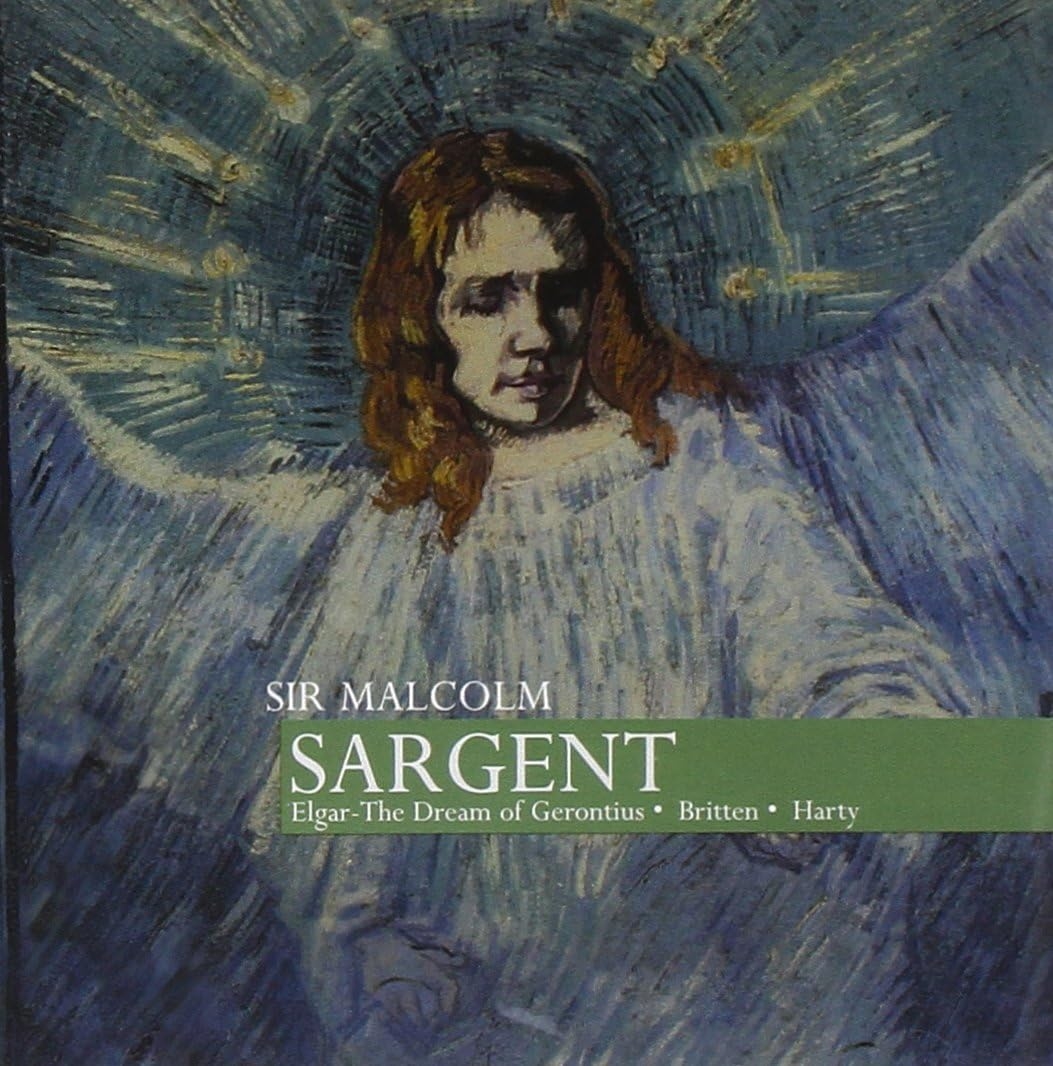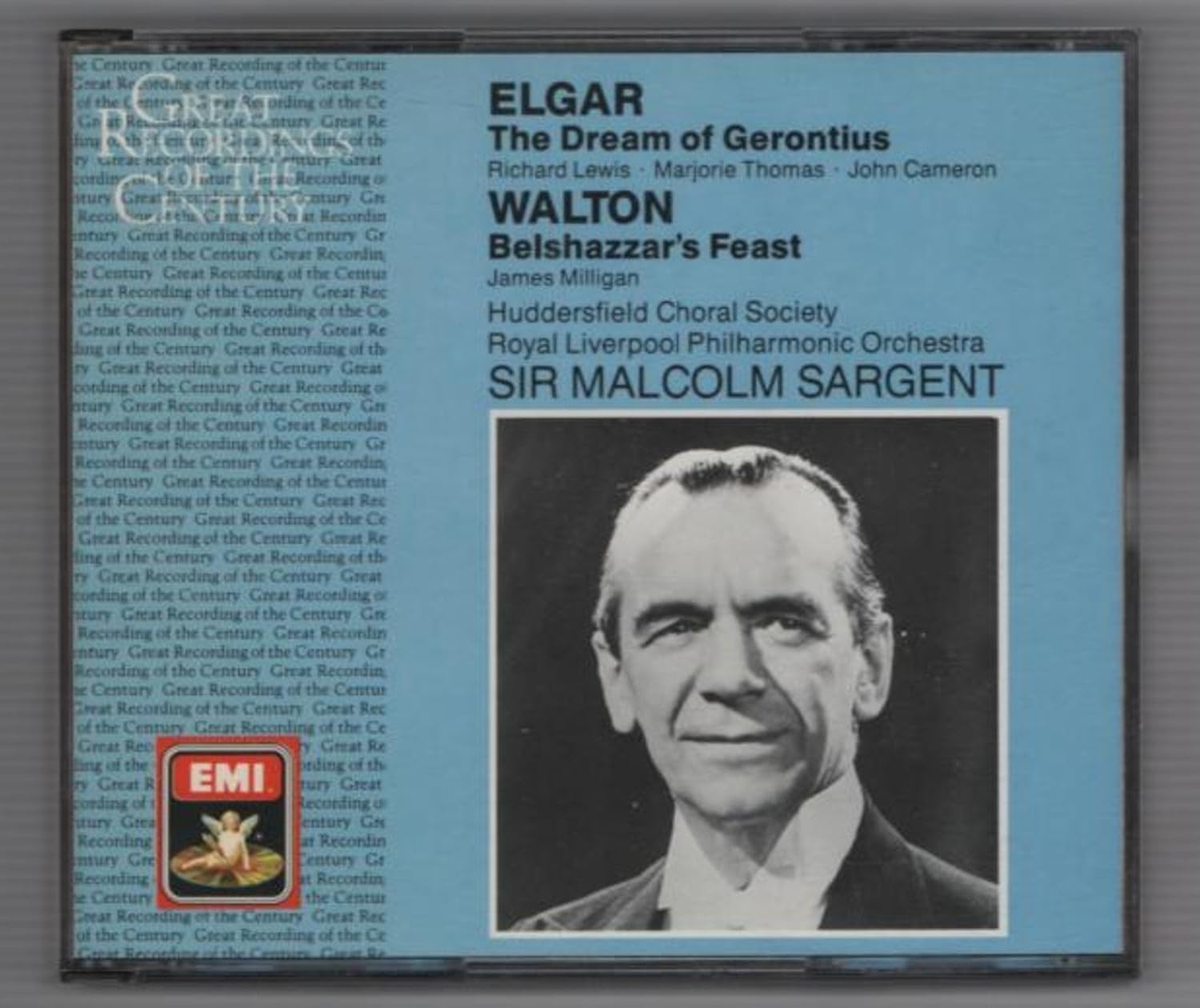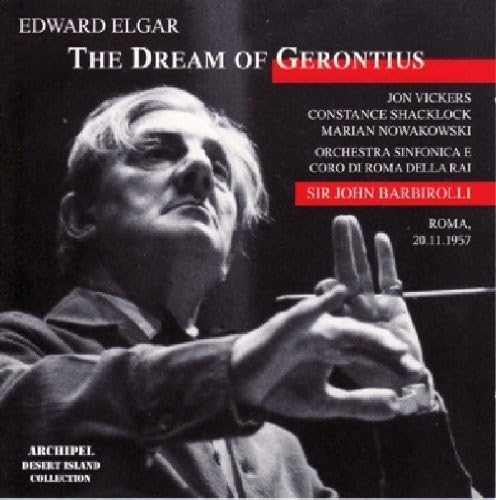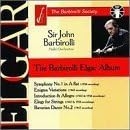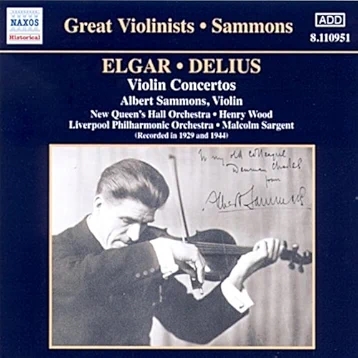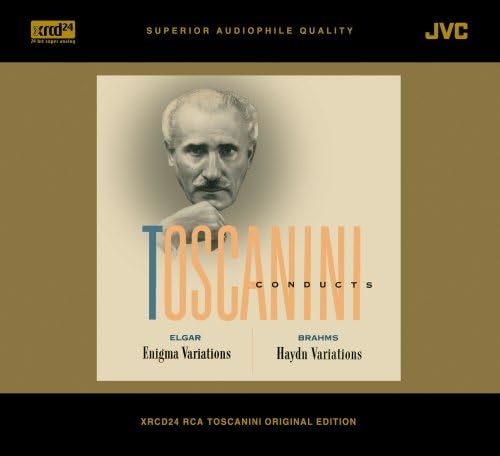エルガー受容史の暗黒時代
英国では絶大な名声を誇るエドワード・エルガーであるが、実は一度だけ彼の作品がほとんど顧みられなくなるという時代があった。
1934年にエルガーが没すると、めっきりと彼の作品がコンサートや録音に取り上げられる回数が激減してしまう。
そんな彼の名声が復活するのは1960年代に入ってからである。きっかけとなったのは例のケン・ラッセル監督のドキュメンタリー「エルガー」が大成功を収めたことによる。
その間、1940年代1950年代はいわばエルガー受容史の暗黒時代なのである。戦争時代を含んでいるという事情もあるだろうが。
この間に、細々とエルガーの功績を伝え続けたのは、やはりボールト、バルビローリ、サージェントらである。
ここであえて、1940から1950年代の暗黒時代の録音をピックアップしてみようと思ってCDを引っ張り出してきたものがこの写真。約20セットというところか。

この中にはサージェントによる「ゲロンティアスの夢」初の全曲録音やトスカニーニによるエニグマ。さらには、カザルス、ロストロポーヴィッチ、ナヴァラ、トゥルトゥリエらによるチェロ協奏曲。ハイフェッツの弾くヴァイオリン協奏曲など注目の録音などが含まれており、思ったよりは多くあることがわかる。
全てを網羅しているわけではないので一概には言えないが、それでも40年代50年代の20年間で約20セットということは1年に1セットはやはり少ない。
しかし、圧倒的にボールトとバルビローリによる仕事が多いのが実情である。彼ら2人は紛れもなくエルガーにとってのヨハネでありパウロであることは間違いない。
それだけにこれらの「暗黒時代」の録音を今改めて感謝と愛を感じながら聴きなおしているところである。
この中で国内盤でリリースされたものは51年2月録音のトスカニーニ指揮、NBC響によるエニグマだけかも。もしかしたらカザルスのチェロ協も国内盤があったかもしれないが見た記憶がない。「暗黒時代」といわれた40、50年代だが、日本などはもっと遥にお寒い状態だったわけである。
この中でボールト5種、バルビローリ5種で最多はこの二人。やはりというところ。ついでサージェントの3種。やはりベスト3はこの3人である。
レーベルでいうとテスタメント5種、EMIが3種で妥当な線か。特にEMI盤のサージェント2度目のゲロンティアス全曲はカップリングがベルシャザールという何とも言えない超豪華な組み合わせだ。これもジャケ買いした1セットである。
ちなみにArkadiaはイタリアの海賊盤レーベルである。そのArkadiaが初めてリリースしたバルビローリ指揮のローマでのゲロンティアスのライブは最近再発されたのだが、久しぶりに聴きなおして、やはりギクっとしてしまった。この盤をお持ちならご存じだと思うが、マイクが指揮者に近いらしく、バルビの唸り声が絶えず入っており、それがあまりにも鮮明なので誰かが話しかけているのかと思ってしまうのだ。音は悪いがすごい臨場感なのである。
ボールトは推進力がハンパない。序奏とアレグロ、南国にて、44年の交響曲2番など凄い生命力。そして、カミソリの切れ味のようなハイフェッツのヴァイオリンなど、やはりすごい。ただハイフェッツの演奏は好き嫌いでいえば大嫌いの部類に入る。
47年のバルビローリによるエニグマは発売当時ポータブルCDに入れて電車に乗りながら聴いていたのだが、フィナーレのあまりの素晴らしさに感動してしまい降りる駅を乗り過ごしてしまったという思い出もある。